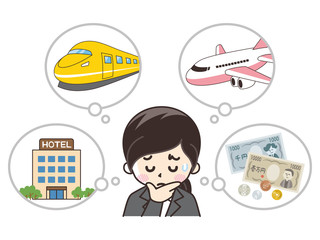減価償却 とは?計算方法やメリットを紹介
減価償却とは、建物や機械、自動車といった固定資産の購入にかかった費用を耐用年数に応じて分散計上する方法のことです。経費を分散することによって毎年の所得を抑えることができるため、節税対策になります。
また、資産を売却すれば会計上の利益を得られるため、財務状況を良く見せたい時にも効果的です。減価償却の方法には定額法と定率法がありますが、それぞれ計算方法が異なるので、確定申告の際には注意しましょう。
節税対策として広く知られている減価償却ですが、初めての確定申告だと「どう計算すればいいのか」「そもそもどんなメリットがあるのか」など、不安や疑問を抱いている方も少なくありません。
そこで今回は、減価償却の基礎知識とメリット、具体的な計算方法についてわかりやすくまとめてみました。
複数年にわたって経費を計上できる!減価償却の基礎知識
減価償却とは、長期にわたって使用される固定資産の購入にかかった費用を分散計上する方法のことです。
ここでいう固定資産とは、オフィスなどの建物や業務に使用する車両・運搬具、工具、機械などの他、牛などの家畜も含まれており、それぞれの耐用年数に応じて減価償却できます。
なお、耐用年数に関しては実際にいつまで使用したのかではなく、資産の種類や構造、用途などを考慮して定めた法定耐用年数が適用される仕組みになっています。
減価償却の計算方法は2種類ある
-1024x683.jpg)
減価償却の計算方法は「定額法」と「定率法」の2種類にわかれています。
購入費を耐用年数で割る「定額法」
定額法とは、資産の購入にかかった費用を耐用年数で割って計算する方法のことです。
たとえば小型の営業車を200万円で購入した場合、耐用年数は4年なので、200万円÷4年=50万円を毎年経費として計上することができます。
なお、建物や建物付属設備、構築物に関しては定額法のみの選択となります。
購入費に一定の償却率をかける「定率法」
定率法とは、保有する固定資産の未償却残高に対し、毎年一定割合を掛けて減価償却額を算出する方法です。
定額法の減価償却額が最初から最後まで変動しないのに対し、定率法は年数が経過するごとに減価償却額が少なくなっていくのが特徴です。
計算式としては固定資産の購入額×定率法の償却率となり、この割合は固定資産の耐用年数によって決められています。
たとえば小型の乗用車なら耐用年数は4年ですので、定額法の償却率は0.500となり、200万円で購入した場合の初年度の減価償却費は200万円×0.500=100万円となります。
定額法と比べると初年度の減価償却費に2倍の開きがあることがわかりますが、次年度以降、償却費はどんどん減っていくので、利益が年々アップしていく場合は定額法に比べて不利となります。
逆に購入年度の収益が大きい場合は、定率法を利用することで初年度の税金を少なく抑えることができます。
定額法を選ぶか定率法を選ぶかは、固定資産のジャンル(建物、車両など)ごとに使い分けることが可能です。
ただ、デフォルトの状態では法人は建物・建物付属設備・構築物以外は定率法。個人は定額法と決まっているので、他の方法で計算したい場合は事前に税務署に届出を提出しておく必要があります。
節税効果や会計上の利益アップに役立つ!減価償却のメリット
減価償却を行うと、経営上、主に3つのメリットを得ることができます。
メリット1. 節税効果が期待できる
減価償却を行うと、資産の購入費用を耐用年数が経過するまで毎年経費として計上することができます。
逆に減価償却を行わなかった場合、資産を購入した年の収益は大幅に減るものの、翌年以降はその恩恵を受けることができません。
収益が上がると、それだけ支払う税金の額も大きくなりますので、減価償却で費用を分散計上した方が安定した経営につながります。
メリット2. 金融機関から正当に審査してもらえる
減価償却を行わない場合、購入年度は大幅な赤字になる一方、翌年以降は一転して黒字経営になるなど、バランスの取れない経営状態となります。
年度ごとの収益に落差があると、金融機関から正当に審査してもらえなくなり、融資時などに弊害になるおそれがあります。
減価償却をしていれば収益の乱高下を防ぐことができ、バランスの良い経営状態を金融機関にアピールすることができます。
メリット3. 会計上の利益をアップできる
減価償却中の資産を売却した場合、減価償却費を差し引いた金額が売却益として計上されます。
実際には売却額が購入費を上回ることはほとんどないので、実際の利益としてはマイナスになるのですが、売却額が減価償却費を下回るケースでなければ会計上は収益をあげることができます。
帳簿では黒字経営となるため、財務状況を良く見せたい時のテクニックとして役立てることが可能です。
【まとめ】
減価償却を上手に活用して税金対策しよう
法人の場合、減価償却は任意ですので必ずしも実施する必要はありませんが、節税効果が高いので、費用の大きな固定資産を購入した時は減価償却を行った方がお得です。
計算式は一見難しそうに思えますが、耐用年数で割るか、あるいは耐用年数に応じた償却率を掛けるかというシンプルなものなので、初めて確定申告する方でも簡単に計算できるでしょう。
らくらく通勤費へのお問い合わせはこちら
関連記事
資料請求や説明のご依頼は、
お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。
東日本:050-5212-5605西日本:06-6412-1190
(営業時間:10:00~12:00・13:00~18:00)



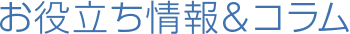

.png)