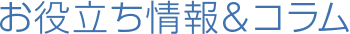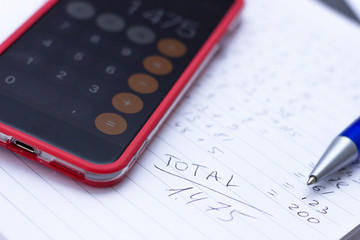交通費精算に 領収書 は必要なのか?
経費精算の申請を行う際に、領収書が必要な場合と、不要な場合があります。特に交通費を精算する場合よくそういった場面に当たると思います。そもそもなぜ不要なのか?領収書はどこまで必要なのでしょうか?
本稿では、交通費を精算する際の領収書に関する気になる疑問を解決していきます。
交通費精算に領収書が必要なケースと不要なケース
一般的に、「少額の電車運賃などは領収書が必要ない」「新幹線利用時など交通費が高額な場合は領収書が必要」と認識している方が多いかと思います。この認識は間違いではありませんが、正確でもありません。まずは、そもそもなぜ領収書が必要か?をご説明していきましょう。
たとえば営業が取引先に訪問するために支払った電車賃は、業務にかかわる費用なので会社の経費として処理する必要があります。処理は原則として、経費を利用した証拠になる書類が必要です。領収書やレシートは証拠(エビデンス)となります。
領収書には取引年月日、取引相手の名前、取引金額、商品名や点数などが記入されるもとのであり、取引先の押印があることで強い証明力を持ちます。営業が領収書を経理担当者に渡せば、それが本当に業務上の経費であるかを確認された上で経費として処理され、精算されます。
さらに、税務上の観点から領収書をしっかりと保管しておくことで、税務署や監査法人に対して「間違いなく会社の経費として使用した」ことを証明する材料になります。
ところが、多くの企業では少額の交通費に関して領収書の提出を不要としているケースがあります。その根拠は、消費税法において「3万円未満(税込み)の場合、領収書の提出は不要」という明確な規定があることです。
“(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)第四十九条
法第三十条第七項 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 . 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
二. 法第三十条第一項 に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき(同項 に規定する帳簿に当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)”
引用:消費税法施行令第49条
このように、3万円未満と取引金額が少額である場合、領収書の提示は求められず、その代わり交通費精算の申請書類を作成し、証憑として保存します。
取引額が3万円以上の場合は、原則として領収書が必要
移動時に新幹線や飛行機など、取引額が3万円以上になる場合は原則として領収書が必要なります。少額の電車賃では難しいかもしれませんが、新幹線となると領収書を発行してもらうのも容易ですし、クレジットカードで決済した場合は明細が残るので、領収書として有効となります。
取引額が3万円を超える場合は社内規定で領収書は不要と定めていても、税務調査において不適切の指摘を受ける可能性が高いので、高額運賃の場合は領収書を発行してもらうことをお勧めします。ただし例外もあります。
先にご紹介した消費税法施行令第49条第2項には「合計額が3万円以上である場合において、同条第七項 に規定する請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」と記載されています。たとえば領収書を発行してもらえるよう頼んだのに、取引先がそれに応じなかった場合などを含めた「やむを得ない理由」があるときは、領収書が無くても経費として処理できます。
その際は、交通費精算申請書にその理由と、支払った取引先が記入されていれば問題ないと定められています。お酒に酔っていて領収書をうっかりもらい忘れた、などの理由では無理ですが、頼んだのに領収書が発行されなかったなどの理由ならば規定に従い、申請書にその旨を記入すれば経費として問題なく処理できます。
交通費の領収書を発行する方法
新幹線などの高額交通費を支払った場合、どのようにして領収書を発行すればよいのでしょうか?まず、係員窓口で新幹線切符を購入した場合は、その場で領収書発行の旨を伝えれば即座に発行してくれます。また、自動券売機で切符を購入した場合は、購入する際に領収書の発行ボタンを押すと領収書が発行される仕組みになっています。
ネットで新幹線の切符を購入した場合はどうなるでしょうか?1つ目の方法は、ネットで切符を予約して券売機で購入し、その際に領収書発行ボタンで発行するものです。そしてもう1つの方法が、チケットレスサービスで購入した場合、ネット上の確認画面から領収書を入手します。
では、切符購入時に領収書をもらい忘れた場合はどうなるのか?切符を利用する前ならば、購入した窓口に申請することで発行されます。ただし、切符を使用して改札を出てしまうと領収書は発行されないので注意しましょう。
新幹線に乗車中に気づいた場合は、改札口で切符が必要であることを申し得ると、切符に無効印が押され、改札に通すことなくそのまま所持することができます。領収書ではありませんが、証憑として残すことは可能です。
領収書の電子データ保存は可能か?
領収書を使った交通費精算を実施する上で欠かせないのが、交通費精算システムです。面倒な精算業務を大幅に効率化して、生産性向上などの効果を発揮します。
たとえば「らくらく旅費経費」は乗換案内サービスとの連携や申請書フォーマットのカスタマイズ、領収書の画像添付機能を含めて20の機能が備わっており、申請者する方の申請手続きや精算業務を行う経理担当者の方の業務処理どちらも大幅に効率化することができます。
各社導入事例を掲載しています。ご興味のある方は導入事例ページをご覧ください。
気になるのは、領収書の電子データ保存は可能か?という点です。結論から言うと、領収書はスマートフォンカメラで撮影し、そのまま電子データとして保存することが認められています。
電子帳簿保存法では、2005年からスキャナによる領収書の電子保存が認められており、2018年からはスマートフォンカメラでの撮影による電子データ化が認められています。これにより、外出先から領収書をその場で撮影して電子データ化し、そのまま経費として申請することができます。
さらに、国税関係書類は法律によって7年間原本を保存しなければいけないと定められていますが、2018年の改正による電子データ化した領収書に関しては、原本を破棄してもよいとされています。
この法令に合わせて「らくらく旅費経費」を使用すれば、営業は外出先にいても領収書をスマートフォンで撮影し、システム上で領収書画像を添付しつつ交通費申請が行えるようになります。営業は移動時間などを利用して申請作業を行えますし、経理担当者としても精算業務が滞らなくなるので、生産性向上などの効果が期待できるでしょう。
交通費精算を見直そう!
1人1台のパソコン利用が普及し、現在では手書きで申請書を作成しているケースはほとんどなくなっているのではないでしょうか。しかし、せっかくパソコンで入力した内容も印刷して処理に回しているケースや、エクセルなどの表計算ソフトで送っていても、結局入力内容の確認は、データを数字として見直している経理担当者の方も多いのではないでしょうか。
こういった一連の処理はかなりの部分を自動化することができ、入力するデータもICカードや「駅すぱあと」連携などを利用でき、もちろんパソコンでなくスマホを利用することで、入力ミスを激減させるばかりか、いつどこからでも申請書を行うことができます。
また、承認フローも自動化し会計システムとも連携できるため、経理担当者の方は届いた申請内容の必要最低限の確認を行うだけで、支払い処理を行うことが可能となります。
当社調査による試算では、従業員300名の企業では申請業務、承認業務、経理業務を合計すると年間約750万円のコストがかかっています。
らくらく旅費経費の利用料は300名で年間249万円ですので、501万円のコスト削減効果が見込まれます。
コスト削減シミュレーターをご利用いただければ、自社のケースでどの程度削減できるかすぐに試算できます。ぜひお試しください。
当社製品については下記よりお問合せ下さい。
お問い合わせはこちら
14日間無料トライアルページ
関連記事
資料請求や説明のご依頼は、
お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。
東日本:050-5212-5605西日本:06-6412-1190
(営業時間:10:00~12:00・13:00~18:00)