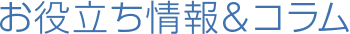【人事】 源泉徴収 とは?仕組みや計算方法をご紹介
源泉徴収という言葉は、多くの人にとってよく見聞きする言葉ではあるものの、実際に源泉徴収とはどんな仕組みなのか、その計算方法はどうなっているのかなど、詳しい内容まで知る人は多くありません。
そんな源泉徴収についてあらためてしっかりと認識するために、ここでは源泉徴収の仕組みやその対象となるもの、計算方法や源泉徴収額を知ることができる書類など、源泉徴収に関する幅広い情報をお届けします。

源泉徴収は、給与や報酬の支払いが生じるやり取りの際に見聞きする言葉ですが、その源泉徴収について、詳しく知っている人はそれほど多くないでしょう。
源泉徴収の仕組みや計算方法とはどんなものか、この機会にここで知っておきましょう。
源泉徴収は、給与や報酬の支払いが生じるやり取りの際に見聞きする言葉ですが、その源泉徴収について、詳しく知っている人はそれほど多くないでしょう。
源泉徴収の仕組みや計算方法とはどんなものか、この機会にここで知っておきましょう。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、毎月の給与所得から所得税を差し引いて、事業者が本人代わって市区町村へ納税することです。従業員へ給与を支払う事業者は、必ず行わなければなりません。
所得税というのは、個人が自分の収入を集計した上でそれにかかる所税金を計算して納付をするというのが本来のスタイル。
ですが、実際にこの手続きを徹底するとなると、個人個人に大きな手間がかかるだけでなく、税務署もその手続き対応に多大な手間をとられてしまいます。
そのため、事業者が本人に代わって納税をおこなっているのです。
源泉徴収とは、この「所得税納付に関する膨大な手間の問題」を軽減するために役立つ制度で、給与や報酬の支払いをする立場のものが、毎月の給与や報酬からあらかじめ所得税分を差し引いておき、それを国に納めるというものです。
給与や報酬の支払いをする立場のものが所得税の計算と納付をある程度のところまでやってくれるという仕組みなので、個人や税務署が所得税納付に関する手間を大きく省くことができるというメリットがあります。
給与や賞与に関する月々の源泉徴収税額に相違が出た分は年末調整で調整し、報酬などに関する源泉徴収額の調整は確定申告で行います。
本来必要な所得税額よりも源泉徴収額が多かった場合は国からその分が還付されますが、源泉徴収額が少なかった場合は年末調整後や確定申告後に不足分を納税する必要があります。
源泉徴収の対象となるもの
源泉徴収は給与や報酬から所得税を差し引くという仕組みですが、すべての報酬に対して適用されるわけではありません。
具体的には、以下のようなものが源泉徴収の対象となります。
*給与・賞与・退職金など
*原稿料・講演料などの報酬
*弁護士・会計士・税理士・司法書士など特定の資格を持つ者への報酬
*社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
*外交員・プロスポーツ選手・モデルなどへの報酬
*芸能人・芸能プロダクションを営む個人への報酬
*ホステスなどへの報酬
*広告宣伝のための賞金・馬主に支払う競馬の賞金
*馬主となっている法人に対する競馬の賞金
源泉徴収の計算方法は支払内容によって異なる
源泉徴収の計算方法は、その源泉徴収の対象となるものが給与なのか報酬なのか、などという形で、支払内容によって異なってきます。
たとえば給与に対する源泉徴収額の計算は、給与額に対して一定の計算式を当てはめるのではなく、国税庁ホームページにある「給与所得の源泉徴収税額表」を参照の上、社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族の数に応じた源泉徴収税額を出していくという形になります。
これに対して報酬に対する源泉徴収額の計算は明確な計算式を用います。
まず、報酬が100万円以下の場合は「報酬支払金額×10.21%=源泉徴収額」となります。
そして報酬が100万円超の場合は「(報酬支払金額-100万円)×20.42%+102,100円=源泉徴収額」となります。
たとえば報酬額が50万円の場合は50万円×10.21%=51,050円が源泉徴収額となり、報酬額が150万円の場合は(150万円-100万円)×20.42%+10万2,100円=20万4,200円が源泉徴収額になるといった形です。
源泉徴収額を知るための書類・源泉徴収票と支払調書
いくら源泉徴収をしているかを従業員や国などに知らせるための書類としては、源泉徴収票と支払調書が挙げられます。
源泉徴収票は、給与や賞与などから源泉徴収をしている従業員に配布するもので、もちろん国にも同じ内容のものが提出されます。
支払調書は原稿料や講演料、税理士や弁護士などの報酬に対して出されるものです。
1年間の支払金額の合計額が5万円超となる場合は、報酬の支払いをする立場のものが支払調書を税務署に提出する義務がありますが、報酬の支払先であるフリーランスや弁護士などへの支払調書発行は特に義務付けられていません。
まとめ:源泉徴収は所得税納付に関する便利な仕組みだが調整も必要
源泉徴収とは、給与や報酬の支払いをするものが所得税を給与や報酬から差し引いた上で納付するという仕組みです。
この源泉徴収の制度を利用することにより、個人の所得税納税の手間などがかなり省けるというメリットがありますが、その納付額と必要な所得税額とに相違が出た分は年末調整や確定申告によって還付を受ける、不足分を納税するなどの調整をする必要があります。
関連記事
資料請求や説明のご依頼は、
お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。
東日本:050-5212-5605西日本:06-6412-1190
(営業時間:10:00~12:00・13:00~18:00)