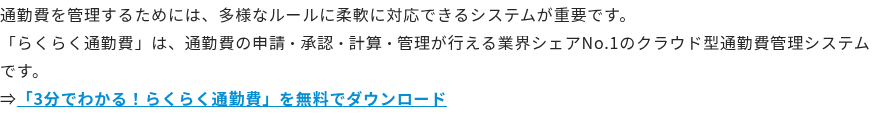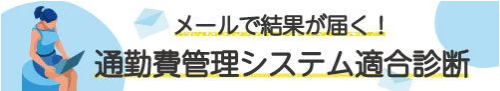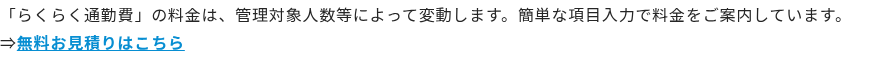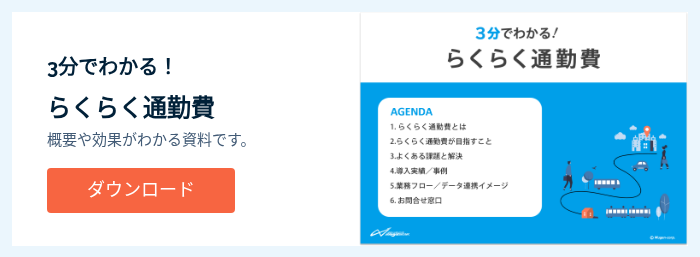通勤費と交通費の違いとは?計算方法や支給時の注意点を解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
「通勤費」と「交通費」の違いと、管理現場の課題を解決する方法を解説します。
通勤費の実費精算は、交通費で処理しても大丈夫か
新型コロナウイルスの感染を防ぐ1つの策として、多くの企業で導入が進んだ「テレワーク」。
以前のコラムで、実施企業の8割以上がテレワークを継続したいとアンケートに回答*¹していることをご紹介しました。出勤日数が減ることにより、定期券を購入するよりも通勤費を実費精算する方が安価になる場合があります。
通勤費を実費精算する際、皆さんの職場では「通勤費」と「交通費」のどちらで処理をされているでしょうか。
結論を言うと通勤費の実費精算は交通費で処理してはいけません。
その理由を説明していきます。
*¹『第2回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査』
(内閣府、令和3年6月4日) 』より
通勤費と交通費の違いとは?
通勤費は給与所得、交通費は経費
通勤費は「通勤交通費」などとも言われ、交通費と混同しやすいのですが、通勤費と交通費には明確な違いがあります。「通勤交通費」「通勤費」を「通勤手当」という表現を使えば、その性質が見えてきます。
他に「手当」と付くものには「残業手当、皆勤手当、役職手当、住居手当、扶養手当」などがあり、そして給与も「給与手当」であることを挙げれば、もうお解かりかと思います。
各種の手当は基本的に従業員の所得とみなされ、人件費となります。つまり、所得税の課税対象や社会保険の計算対象となります。通勤費は、非課税の場合もありますが詳しくは後述します。
通勤費は自宅から勤務地までの通勤のためにかかる費用の一部または全額を、福利厚生の一種として手当で会社が支払います。
一方の交通費は、業務上の移動にかかる費用で、従業員が取引先や関係施設などを訪問する際に利用する交通機関の料金(電車賃、バス代、飛行機代、タクシー運賃、業務で使用した車のガソリン代など)が該当します。経費の扱いとなり勘定科目では旅費交通費や出張旅費等で処理します。
所得なら社会保険料にも影響
通勤費は一定の限度額までは非課税ですが、それを超えると所得税の課税対象となります。
鉄道・バスなど交通機関の定期代等の非課税限度額は月15万円*²です。ただし、企業によっては通勤費の支給上限額を15万円よりも少ない額とし、上限を超過する分は自己負担としている場合もあります。
所得税がかからないのであれば経費と同じと考えて、経費精算にて処理することには問題があります。「本来納めるべき所得税を納めていない」「社会保険料を不当に下げている」と判断される恐れがあるからです。
非課税が認められる通勤費ですが、社会保険(健康保険、雇用保険、厚生年金、厚生年金基金、介護保険)の算定計算対象になります。その他の給与手当と合わせて社会保険料計算の根拠となります。
*²『通勤手当の非課税限度額の引上げについて(国税庁、平成28年4月) 』より
| 名目 | 分類 | 所得税・住民税 | 社会保険料 |
| 通勤費 | 人件費 | 対象(限度額まで非課税) | 対象 |
| 交通費 | 経費 | 対象外 |
対象外 |
関連記事 「社会保険料の算定の為に、簡単・正確な通勤費管理を」
交通費の種類
通勤交通費と旅費交通費のそれぞれの違いをまとめます。
通勤交通費
通勤交通費は通勤費や通勤手当とも言います。自宅から勤務地までの通勤のためにかかる費用(きっぷ代や定期代、ガソリン代など)の一部または全額を、福利厚生の一種として手当で会社が支払います。
ほとんどの企業が通勤費を支給していますが、企業には通勤費の支給義務はありません。ただし、就業規則等に規定した場合には支給しなければなりません。
また、通勤費は一定の条件を満たせば課税所得になりませんが、他の手当と同様に社会保険料の算定対象となります。
旅費交通費
交通費は旅費交通費とも言い、従業員が出張や移動など業務上で発生する移動費用や宿泊などの経費を指します。具体的には、電車、バス、飛行機、新幹線、タクシー等の交通機関の運賃やレンタカー料金、ガソリン代、高速道路料金や宿泊費などが含まれます。
立て替えてた交通費は、所得税や社会保険料の計算には関係しません。通勤費と似ていますが、混同しないように気を付けましょう。
社会保険料と通勤費・交通費
通勤費は、社会保険料と密接な関係にあります。
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の金額は、基本的に企業が年に一度届け出る“算定基礎届”によって決定されます。この算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を見直すための手続きです。
標準報酬月額は、その年の4~6月の3ヶ月間の報酬額をもとに算出され、この報酬額には基本給の他、通勤費をはじめとする諸手当が含まれます。ここで求めた標準報酬月額から1年間の社会保険料が決定されます。
報酬が高ければ社会保険料が上がりますので、通勤費の額が大きいほど社会保険料が多くなります。
一方、旅費交通費は業務の為の移動に掛かる交通費で経費ですので、社会保険料には関係しません。
所得税と通勤費・交通費
給与から源泉徴収される所得税・住民税は、給与の合計額から社会保険料等の各種控除額を差し引いて決定されます。
通勤費は、原則として給与と見なされるため、所得税の課税対象です。ただし、利用交通手段の金額や距離に応じて非課税限度額が定められており、その額を上回らない限りは課税されません。非課税限度額を上回った場合は、超過分が課税対象となります。実際は、非課税限度額内で通勤費が支給されていることが多いので、通勤費は非課税という感覚の方が多いかと思います。
旅費交通費は所得税の課税対象にはなりません。経費精算は、会社が払うべき経費を従業員が立て替えたため実費で弁償することなので、手当を支給することとは性質が異なるためです。
通勤費の非課税限度額について
繰り返しになりますが、通勤費も給与の一部なので所得税の課税対象です。しかし実質的には非課税限度額内で支給されていることが多く、通勤は非課税であるという認識の方が多いと思います。
「経済的かつ合理的」な経路における通勤費に対して非課税限度額が定められています。時間の短さや金額の安さを比較し判断を行います。
鉄道・バスなどの交通機関の利用の場合や、マイカーなどの交通用具で有料道路を利用する場合には、1ヶ月当たり15万円までが非課税として認められています。
マイカー・バイク・自転車等の交通用具は、片道距離で区分され38,700円を上限に非課税の額が定められています。
非課税限度額の条件がどのようなものか、以下で解説します。
交通機関や高速道路を利用する場合
公共交通機関(鉄道、バス等)を利用する場合の定期代やきっぷ代で、1ヶ月当たり15万円までが非課税となります。長距離通勤で新幹線を利用する場合も合理的な理由があれば認められます。ただし、グリーン券は非課税と認められません。また、合理的な理由なく遠回りで高額な経路を利用する場合も非課税と認められません。
3ヶ月定期や6ヶ月定期を支給されている場合は、1ヶ月当たりの金額を求め15万円未満であれば非課税となります。
下表の3.がそれに該当します。
マイカーなどの交通用具で有料道路を利用して通勤する場合も、15万円までの非課税限度額が認められています。
下表の1.がそれに該当します。
下表の2.4.については後述します。
- 1か月に支給される通勤手当が15万円を超えない場合
| 区分 | 課税されない限度額 |
| 1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 最大38,700円 |
| 3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
マイカー・バイクを利用する場合
上の表の「2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」では、マイカー・バイクなどの交通用具での通勤をしている場合の上限を38,700円とされていますが、距離区分に応じて非課税限度額が設定されています(下表参照)。
特に、2km未満の場合は非課税はなく全額課税通勤費となります。
2km未満は通勤手当を支給しないという企業がほとんどです。
下表の非課税限度額を超過した場合は、超過分が給与所得として課税されます。
- 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額
| 区分 | 課税されない限度額 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満 | (全額課税) | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 | |
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,900円 | |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,300円 | |
| 通勤距離が片道55キロメートル以上 | 38,700円 |
公共交通機関と自動車を併用する場合
上記の表にて「4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券」 の場合も15万円までが非課税限度額となっています。
例えば、自宅から駅まで遠くバスが無い地域の通勤で「自宅から駅まで自動車で移動し駅前に駐車、駅から勤務先まで鉄道で通勤」といったケースです。
マイカーのガソリン代の計算方法などは企業ごとの就業規則等で規定します。
通勤費運用時の注意点
繰り返し述べていますが、企業に通勤費の支給義務が無い為に、通勤費の支給や運用は就業規則等でルールを明確にしておかなければなりません。
実費支給か定期代支給かを明確にする
週5日で出社勤務であれば定期代支給で問題ないかと思いますが、テレワークであったりパートタイム勤務の場合ではきっぷ代等の実費支給と定期代支給の切り分けを明確にしておく必要があります。
また、経路によっては定期代と実費で最安経路が異なる場合がありますので、「経済的かつ合理的」な経路の基準を決めておく必要もあります。
「最短経路のみ」や「最安経路のみ」とするよりも、「最安経路の金額から○○%以内」や「最安経路よりも〇〇分早くなる経路」を認めるなど「経済的かつ合理的」を数値化することで、判断の属人化やトラブルを防げます。
また、障がいや特別な事情を持っている従業員などへの対応についても、規定を整備すべきです。
計算方法を明確にする
「経済的かつ合理的」な経路における通勤費の支給のためには、計算方法を明確にする必要があります。
定期代やきっぷ代を支給する場合には、自宅や勤務地から最寄り駅までの距離および計測方法を定めます。
道なりか、直線距離か。バス利用の場合の距離は○○km以上か。測定ツールは何を利用するかなどです。
距離の計測方法を決めたら、それに基づいて候補駅を利用した経路による金額を計算します。
転居、転勤、退職に伴う定期代の払い戻しの場合は、鉄道は月割り、バスは日割りや、同一鉄道会社での経路変更であれば旬割などの計算方法がありますが、交通機関に合わせた払い戻し計算にするのか会社独自のルールにするのかを定めます。
マイカー通勤など交通用具においては、キロメートル単価にするか、燃費基準を設定した計算式か、距離範囲での金額表による支給にするかなどを定めます。車種別に燃費が異なる支給を設定する方法もあります。
通勤手段によって計算方法が異なりますが、就業規則等に規定することにより従業員とのトラブルの防止や効率的な運用への効果が見込めます。
支給タイミングを明確にする
支給期間、支給対象月、支給開始月などは定期代支給と実費支給とでは異なるので、通勤費の支給タイミングも異なります。
支給期間としては1ヶ月定期と6ヶ月定期、実費支給による違いがあります。
支払対象月は、前払い、当月払い、後払いがあります。
支給開始月は、1か月定期や実費支給であれば毎月の処理ですが、6ヶ月定期の場合は支給開始月を4月・10月などに固定するか、従業員ごとに開始月が異なるかで処理する月に違いがあります。
そして、更新時に申請が必要かどうかなども含め、業務負荷やコスト削減の観点で支給タイミングを決める必要があります。
支給タイミングについて、下記の表にまとめました。
| 支給期間 | 支払対象 | 支給月 | 更新時申請 | 特徴 |
| 1ヶ月定期 | 前払い、当月払い | 毎月 | 不要 | 毎月処理、割高 |
| 6ヶ月定期 | 前払い、当月払い |
3・9月給与 4・10月給与 |
不要 | 決まった月に処理ができ業務の集約化ができるが、変更時には端数月で計算必要 |
| 6ヶ月定期 | 前払い、当月払い | 毎月 | 不要 | 毎月処理、割安、変更時に6ヶ月定期支給 |
| 実費支給 | 当月払い、後払い | 毎月 | 必要 | 勤怠との突合必要 |
通勤費の支給を効率化するためには、管理システムの導入が有効
通勤費支給を効率化するためにおすすめしたいのが「通勤費管理システム」です。
通勤費管理の業務でもっとも負担の大きい作業は何か?それは、従業員から申請された通勤ルートや金額に間違いが無いか、担当者が1つ1つインターネットなどで調べて確認する作業ではないでしょうか?
対象人数が多いと手間が大きく、手作業では判断に迷いが生じたりミスが起こりやすくなったりします。
しかし、通勤費管理に特化したシステム「らくらく通勤費」なら、このような作業負担をサポートし、軽減してくれます。
申請の検証や自動支給も可能に
通勤費管理システムは、従業員の自宅や会社の住所を取り込んで利用すべき駅や経路を適切に導き出すことが可能です。また、バス利用が会社の規定に照らして可能かどうかの判断までできます。マイカー通勤の管理に関しては、通勤ルートと距離測定、燃料代変動への対応などを簡単に行うことが出来ます。
通勤費の支給基準は、すべての会社が同じではありません。独自に決めることができる*³からです。会社ごとの独自の規定をシステムに設定することで、適正かつ業務負荷の少ない処理が可能になります。また、全従業員が規定に則った申請ができますので、支給内容の不公平なども是正されます。
さらに、出勤データと紐づけると、出社日数による実費通勤費を自動で算出、支給ができテレワークなどの勤務形態への対応にも心配することはありません。
*³その際、公務員の規定(第六条)を参考にする企業が多いようです。
『人事院規則九―二四(通勤手当)(令和二年六月十二日) 』より

人手にコストをかけるよりも、通勤費管理はシステム化するべき
「確かに通勤費管理システムはいい、けれど費用がねぇ…」「システム導入に手間がかかりそうだ」と二の足を踏む管理者や経営者の方々もいらっしゃることでしょう。しかし、管理業務を担う部門の業務が増えれば、その手間は残業代や人員補充によるコストになります。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」ならクラウドで簡単に導入することができ、業務コストの削減に大いに貢献します。
まとめ
通勤費と交通費は混同されがちですが、通勤の為に使用する交通費を給与手当として支給するのが通勤費であり、業務で使用する交通費を経費として処理するのが交通費です。
ほとんどの企業が支給している通勤費ですが、企業に支給義務はありません。就業規則等で規定した場合には、支給義務が発生します。通勤費には所得税や社会保険の計算が必要で、誤って処理すると税務上の問題が生じる可能性があります。
テレワークの普及や働き方の多様化に伴い通勤費の支給管理業務は煩雑化していますので、通勤費管理システムの導入による業務効率化が有効です。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」なら、通勤費の支給管理の簡略化・効率化が実現できます。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。