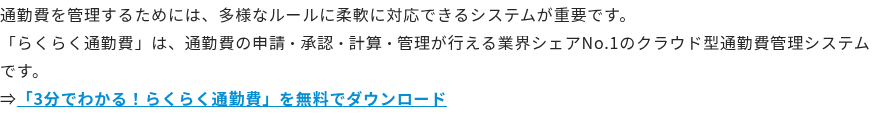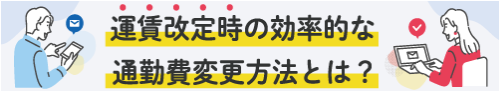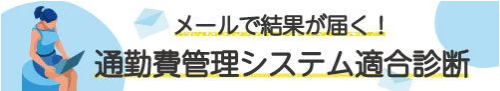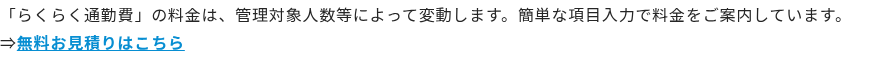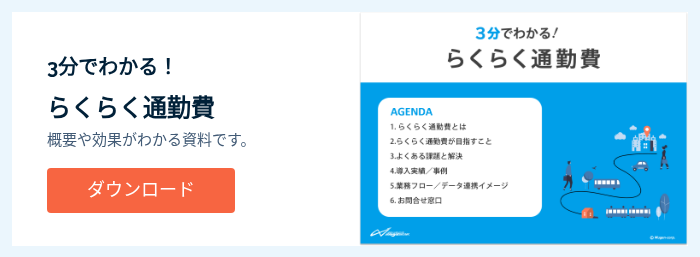定期券の払い戻し条件と計算方法のポイントを解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
毎日鉄道・バスで通勤する場合は、定期券を購入したほうが安価なのは皆さんもご存知かと思います。
ほとんどの企業では、通勤で使用する交通費を通勤手当として支給しているので、安価で通用期間ごとに固定額を支給すればいい定期券は企業の強い味方です。
しかし、転居、転勤、退職、実費支給への切り替えなどにより定期券を払い戻す場合は少しルールが複雑です。
今回は、通勤手当の計算や管理をする人事・総務・労務担当者様の役に立つ定期券の種類ごとの払い戻しの計算方法や、流れを解説します。
なお、一般的な鉄道定期券の払い戻し計算について記載していますので、具体的な払い戻し計算については個別に確認いただくことをおすすめします。
定期券の払い戻し(途中解約)が可能な期間
定期券の払い戻しで、有効期間別に途中解約可能な期間は以下の通りです。
| 有効期間 | 払い戻し可能な期間 |
| 1ヶ月 | 使用開始日から7日以内 |
| 3ヶ月 | 使用開始日から2ヶ月以内 |
| 6ヶ月 | 使用開始日から5ヶ月以内 |
1ヶ月定期券は、やむを得ない理由により解約をする場合に限り使用開始日から7日以内であれば払い戻しが認められます。3ヶ月・6ヶ月定期券は、有効期間が1ヶ月以上残っていることが条件となり、これは払い戻し額が月割で計算されることによります。
定期券の払い戻しはこのように条件が複雑なため、企業によっては独自の払い戻し条件を定めている場合があります。例えば、払い戻しは無条件に月割で解約計算とすることで払い戻し条件の確認の手間を省くというケースがあります。
払い戻し手続きについては就業規則等の内容を従業員への周知徹底し、従業員と管理者双方の認識違いが出ないよう注意が必要です。
鉄道定期券の払い戻し計算方法
鉄道定期券を払い戻す際は、月割計算が基本となります。
JR東日本のFAQページに定期券の払い戻し金額や条件について記載があります。以下抜粋します。
“不要となった定期券は、有効期間が1ヶ月以上残っている場合に限って払い戻しいたします。この場合の払い戻し額は、発売額からすでにお使いになった月数分(1ヶ月に満たない日の端数は1ヶ月とします)の定期運賃と手数料220円を差し引いた残額です。ただし、払い戻し額がない場合もあります。
払い額=定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料220円例)
有効期間が4月1日から9月30日までの6カ月定期券を8月20日に払い戻す場合払い額=6カ月定期運賃-(3カ月定期運賃+1カ月定期運賃×2)-手数料220円”
定期券は1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月がありますが、それぞれの計算方法を見ていきます。
1ヶ月定期券の払い戻し計算方法
1ヶ月定期券の払い戻し額は、以下の式で算出されます。
定期券発売額 −(定期区間の往復運賃 × 経過日数)− 手数料 = 払い戻し額
途中解約は、買い間違いなどのやむを得ない理由により「使用開始日から7日以内」に限られ、使用開始日も日数に含まれる点に注意が必要です。払い戻しのタイミングが1日でも遅れると対象外となり払い戻し額が0円になってしまいます。窓口での払い戻し手続きには日付の確認が大事です。
3ヶ月定期券の払い戻し計算方法
払い戻し日によって計算方法が異なります。以下の表をご参照ください。
| 払い戻し日 | 計算式 |
| 使用開始から7日以内 | 3ヶ月定期券発売額 −(定期区間の往復運賃 × 経過日数)− 手数料 |
| 使用開始から8日以降 | 3ヶ月定期券代 −(1ヶ月定期券代 × 経過月数)− 手数料 |
7日以内の払い戻しは、1ヶ月定期と同様に経過日数で計算されます。
払い戻し額は日数や月数で大きく変動するため、払い戻し日がいつかを正確に確認することが重要です。
6ヶ月定期券の払い戻し計算方法
6ヶ月定期券の場合は、以下の条件で計算されます。
6ヶ月定期券発売額-使用済月数分の定期運賃-手数料
使用済み月数によって、1ヶ月~5ヶ月分までの定期運賃の組合せが異なりますので注意が必要です。
6ヶ月定期券(6万円)を4月1日に購入した場合の、払い戻し額のシミュレーションは、以下の表の通りです。
| 払い戻し申請日 | 払い戻し額計算式例 |
| 4月20日 | 6万円 ー 1ヶ月分の定期代 ー 手数料220円 |
| 5月20日 | 6万円 ー(1ヶ月分の定期代×2) ー 手数料220円 |
| 6月20日 | 6万円 ー 3ヶ月分の定期代 ー 手数料220円 |
| 7月20日 | 6万円 ー(3ヶ月分の定期代+1ヶ月分の定期代) ー 手数料220円 |
| 8月20日 | 6万円 ー(3ヶ月分の定期代+1ヶ月の定期代×2) ー 手数料220円 |
| 9月20日 | 払い戻し不可 |
※1ヶ月に満たない端数は1ヶ月として扱われます(月割計算)。
定期券の払い戻し金額および条件は、上記の表のように変化します。たとえば、4月1日購入の6ヶ月定期券は9月30日までの利用が前提です。
9月20日の時点では残り10日ですが、1ヶ月未満の端数は1ヶ月とみなされるため、払い戻しは不可となります。
つまり、9月1日の時点で残り1ヶ月未満と判断され、その日以降は払い戻しできません。
定期券の払い戻しを検討する際は、払い戻し日と残り期間の関係に十分に注意が必要です。
<例>
武蔵浦和~新宿間の6ヶ月定期券(59,120円)を4月1日に購入した場合の払い戻し例です。
■7月1日~7月31日に払い戻す場合
計算式:6ヶ月定期代59,120円-(3ヶ月定期代35,050円+1ヶ月定期代12,290円)-手数料220円
⇒払い戻し額:11,560円
■8月1日~8月31日に払い戻す場合
計算式:6ヶ月定期代59,120円-(3カ月定期券35,050円+1カ月定期代12,290円×2)-手数料220円
⇒計算結果:-730円(※払い戻し額は0円)
このように、残りの利用期間が少ない場合は、払い戻し額が0円になる可能性があります。
定期券の払い戻しについて、月割り計算や残期間の扱いなど注意点が多くあります。
詳しくは以下の記事も参考にしてください。
参考:定期券の払い戻し ルールとシステムの有用性
1ヶ月定期券の払い戻しはできないのか?
「1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とする」というルールから、1ヶ月定期券は購入時点で満期とみなされ、基本的には払い戻し不可となります。
しかし、以下の条件を満たす場合は、払い戻しが可能です。
購入間違いによる直後の申請
利用区間の誤りなど、購入直後に申請すれば、鉄道会社によっては全額払い戻しされることがあります。重要なのは「その場で申請する」ことです。
ただし、購入間違いは利用者の過失であり、鉄道会社に対応義務はありません。対応可否は各社のルール次第で、払い戻しされない場合もあります。
使用開始日から7日以内の申請(JR東日本)
JR東日本では、使用開始日から7日以内に払い戻し申請を行った場合に関しては、特別なルールが設けられています。これは購入間違いをしてしまった利用者に向けてルールであり、以下のように定められています。
“買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券が不要となった場合は、有効期間の開始後7日以内に限り、発売額からすでに経過した日数分の往復普通運賃と手数料220円を差し引いた残額を払いもどすことがあります。”
たとえば4月1日に1ヶ月定期券を購入し、間違いに気づいて4月6日に払い戻しの申請を行った場合は、4月6日時点で6日間が経過したことになります。よって、普通に乗車した場合の運賃(往復分)の6日分と、手数料220円を差し引いた金額が払い戻しされます。
<例>
武蔵浦和~新宿間の1ヶ月定期券(12,290円)を4月1日に購入した場合の払い戻し例です。
■4月6日に払い戻す場合
・片道運賃:切符料金410円
計算式:1ヶ月定期券12,290円-(410円 × 2(往復) × 6日分)-手数料220円
⇒払い戻し額:7,150円
7日以内であれば利用した日数分の往復運賃を差し引いた金額で払い戻しができますが、鉄道会社の判断によるため窓口での確認が必要です。
区間変更による払い戻し
転居や異動などで同一路線上の別の駅に変更とする場合は、新しい定期券の購入と同時に払い戻しを行うことで区間変更扱いとなります。この場合は一定額の払い戻しが可能です。
“新しい区間の定期券をお求めいただき、古い区間の定期券は払い戻しをいたします。この場合の払い戻し額は、発売額からすでにお使いになった旬数(10日を1旬とし、1旬に満たない日の端数は1旬とします)に定期運賃の日割額を10倍した額を乗じた額と手数料220円を差し引いた残額です。”
引用:
JR東日本 きっぷのあれこれ きっぷの払い戻し
定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし
「新しい区間の定期券を購入することを条件に、古い定期券に支払った金額のうち一定額を払い戻します」というルールです。ポイントは“旬数(じゅんすう)”です。これは10日単位を意味し、旬数に応じた払い戻しがされます。
<例>
武蔵浦和〜新宿間の1ヶ月定期券(12,290円)を4月1日に購入し、4月20日に新しい定期券を購入し古い定期券を払い戻しする場合の例です。
計算式:1ヶ月定期券12,290円-( 1旬(12,290÷30×10)×2(2旬分))-手数料220円
⇒払い戻し額:3,870円
※新しい定期代は例に含めていません。
このように、1ヶ月定期券でも条件を満たせば払い戻しが可能です。
ただし、対応は鉄道会社の判断によるため、必ず窓口で確認することが大切です。
定期券の払い戻し手続きの流れ
定期券の払い戻しは、利用する交通機関によって手続き方法が異なります。
鉄道定期券の場合は、発行元の鉄道事業者の駅にある定期券窓口で申請できます。バス定期券は、各バス会社の営業所窓口で対応しています。
モバイルICカード(モバイルSuica・モバイルPASMOなど)の定期券は、専用アプリ上で手続きが可能です。申請後は、内容確認と払い戻し額の計算が行われ、問題がなければすぐに現金または指定口座への振込で返金されます。
払い戻し手続きは、交通機関ごとに対応ルールが異なるため、事前確認が重要です。
払い戻し申請に必要な書類
定期券の払い戻しには、以下の書類が必要です。
・使用していた定期券
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、顔写真付き学生証・社員証・住民基本台帳カードなど)
まとめ
以上のように、定期券の払い戻しには「月割」「旬割」「日割」など、利用する交通機関や条件によってさまざまな計算方法があり、定期券の期間によっても計算すべき方法が異なります。
転居や転勤、入退職に伴う払い戻し計算はなかなか手間のかかり、大変だと感じる担当者が多い業務の一つです。通勤費管理システムの「らくらく通勤費」を利用すれば、払い戻し日を入力するだけで利用する公共交通機関のルールに合わせた払い戻し計算が簡単に行えます。払戻手数料も加味して自動計算できます。
従業員からの払い戻し申請と、管理者による払い戻し処理のどちらにも対応しています。
定期券の払い戻し計算だけでなく、新たに通勤経路の申請や登録をする際の経路の判断も、地図や乗換探索エンジンを組み込んでいるので簡単かつ正確に行うことができます。
まだ通勤費管理をシステム化していない企業様は、「らくらく通勤費」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。