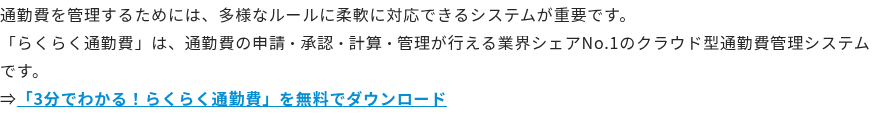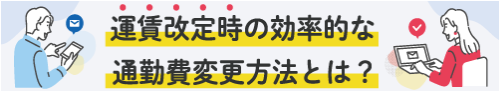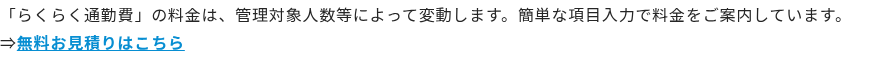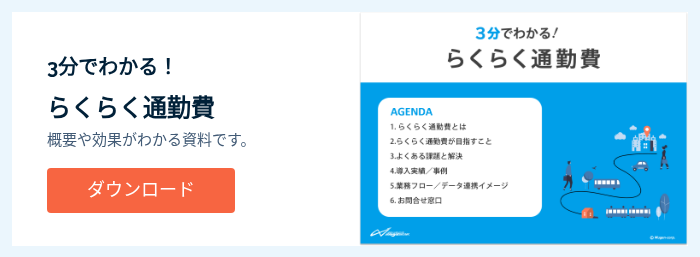通勤費の支給ルール、貴社はどうされていますか?
監修者:佐川豊
この記事の目次
通勤手当を支給するための規定では、一般的に『通勤時において最も経済的かつ合理的と考えられる経路、手段に基づいて算出する。』としている企業が多いです。しかし、細かいルールや、どの交通手段を認めるかは企業によって異なります。
あまり多くないですが、自転車や徒歩の通勤に対しても手当を支給している企業もあります。
今回は、そういった様々な支給ルールについてどのようなものがあるのか紹介していきたいと思います。
①鉄道定期代の支給ルール
・最安定期代の経路から金額または%で許容範囲を設ける
・最短の経路から時間または%で許容範囲を設ける
・最安定期代経路から、xx分以上早い経路がある場合には、金額が高い場合でも最短経路を認める
・コスト削減の為、最安経路しか認めない
② バス定期代の支給ルール
・自宅住所~最寄駅までの距離を計測し、規定の距離内に駅がない場合バスの利用を認める。
・距離は直線距離とする。
・自宅住所~最寄駅までの実走距離
・最寄バス停~最寄駅までのバス路線の距離
一つ目の「自宅住所~最寄駅までの距離」の判断基準としては、1.2kmもしくは1.5kmが多くの企業で採用されています。
③マイカー通勤支給ルール
・自宅住所~勤務地住所までの実走距離に基づき支給する。
・自宅住所~勤務地住所までの直線距離または道なり距離
・自宅住所~勤務地住所までの直線距離または道なり距離に一定係数を掛ける
・公共交通機関を利用したとみなし定期代相当額で支給する
距離計測方法と計算方法は、会社によって異なります。
km当たりの単価設定や、地域のガソリン単価と平均燃費を決めて算出する方法、または交通用具の非課税限度額内で支給するなどの計算方法などがあります。
④その他支給ルール
自転車通勤手当&徒歩手当支給している会社では、以下のようなケースがあります。
・走行距離または直線距離が2Km以上のみ支給
・「〇km~△kmまでいくら」のような距離テーブルに沿った支給
・一律金額を支給
・駐輪場代の支給
通勤手当の支給・管理をシステムで効率化
ご紹介した中に貴社のルールはありましたでしょうか。
もしかすると、「自社のルールは少し複雑だ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」は、シンプルな支給ルールから複雑な支給ルールまで対応できるシステムです。通勤費の申請・承認・計算・管理ができ、住所 to 住所の経路検索で最適経路が一目でわかるので申請者も管理者も納得の通勤費支給を実現します。
通勤手当の管理に手間を感じられていたら、是非一度システム化をご検討ください。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。