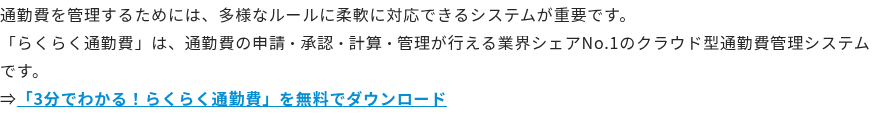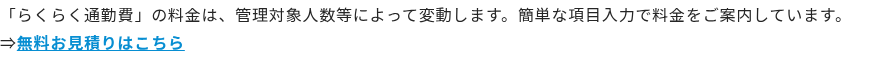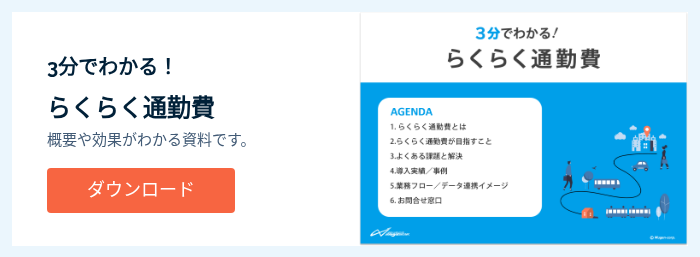通勤手当の決め方を解説!通勤手段別の決め方や距離の測り方を紹介
監修者:佐川豊
この記事の目次
通勤手当はほとんどの企業で支給されていますが、企業ごとに通勤手当の支給方法は異なります。自社の通勤手当の支給方法が一般的なのか、または適正なのかなどが気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、一般的な通勤手当の決め方や距離の測り方、支給時の注意点などを解説します。
労働基準法において通勤手当の規定はない
通勤手当は、通勤にかかる交通費を支弁するための手当であり、労働基準法上の「賃金」の一部にあたります。
しかし、企業側に通勤手当を支給する義務はなく、労働基準法には通勤手当をどのように支給するべきかを定めた規定がありません。
支給義務はないものの、多くの企業が福利厚生の一環として通勤手当を支給しています。
令和2年に厚生労働省が行った「就労条件総合調査」では、諸手当を支給している企業のなかで「通勤手当など」を支給している割合は92.3%というデータもあります。
参照:厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」
通勤手当の決め方について
前述のとおり労働基準法には通勤手当の支給に関する規定がありませんが、多くの企業では「経済的かつ合理的な経路および方法」で支給しています。
理由は、通勤手当が非課税になるのは「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で支給されていることが条件とされているためです。
細かなルールは企業ごとに異なりますが、一般的な通勤手当の決め方をご紹介します。
通勤手当の基本要件を定める
通勤手当を支給するためには、まずは基本要件が必要になります。支給方法や金額、通勤手段、距離による条件などを定めます。企業の業種・業態や、勤務地の立地によって最適な要件が変わります。それぞれの項目の一般的な例をいくつかご紹介します。
<支給方法や金額>
・通勤にかかる費用を全額支給する
・通勤距離にかかわらず、全従業員に一律金額を支給する
・支給額に上限を設け、上限までの金額を支給する
<通勤手段>
・公共交通機関(電車・バスなど)
・交通用具(自動車・バイク・自転車など)
・公共交通機関と交通用具の併用(駅まで自動車に乗り、駅から電車など)
・徒歩
<距離による条件>
・交通用具を利用する場合は、道なり距離が2キロ以上のみ支給対象とする
・交通用具を利用する場合は、「距離×ガソリン単価(または燃費)」で計算する
・交通用具を利用する場合は、「2キロ~10キロ未満は4,200円」など距離区間ごとに支給額を決める
・自宅や勤務地から最寄り駅までの距離が1.5キロ以上離れている場合のみバスの利用を認める
<その他の詳細条件>
・交通用具を利用する場合は、免許証、任意保険証、車検証などの証明書の提出を必須とする
・定期代支給対象者は、購入証明書の提出を必須とする
・公共交通機関を利用する場合は、基本的に最安の経路を採用するが、15分以上早い経路は認める
電車・バス通勤を認める場合の決め方
電車・バス通勤は、出社日数が少ない場合は実費支給、出社日数が多い場合は定期代支給をするのが一般的です。企業によっては部署や個人ごとに出社日数が全く異なるため、実費支給と定期代支給が混在しているケースもあります。多くの企業で実費支給は後払い、定期代支給は前払いにしていることもあり、混在していると支給や管理にかかる手間は一気に跳ね上がります。
また、定期代を支給する場合は、途中で定期券を解約する場合の精算についてもルールの整備が必要です。定期券の解約時に戻る金額相当を精算しない企業も稀にありますが、多くの企業では通勤が必要なくなる日をもとに払い戻し金額を計算して精算しています。
そして電車・バス通勤を認める際に大変なのが「経済的かつ合理的な経路」の判断です。
経路の妥当性をチェックする人が複数名いても同様の判断ができ、なおかつ申請する従業員にも理解しやすくするためには「最安のみ認める」や「最安よりも15分以上早い経路は認める」など具体的なルールを設定するとよいでしょう。
バスの利用を認める際の条件として、「自宅から最寄り駅までの距離が1.5キロ以上離れている場合のみバスの利用を認める」のようなルールを設けている企業も多いです。
「経済的かつ合理的な経路」の判断は、一定額まで通勤手当を非課税として処理できるだけでなく、従業員同士の公平性の担保や企業のコスト削減にも繋がります。
自動車・バイク通勤を認める場合の決め方
自動車・バイク通勤の通勤手当の計算方法は、主に以下の3種類があります。
・通勤距離にかかわらず、全従業員に一律金額を支給する方法
・交通用具を利用する場合は、「距離×ガソリン単価(または燃費)」で計算する方法
・交通用具を利用する場合は、「2キロ~10キロ未満は4,200円」など距離区間ごとに支給額を決める方法
詳しくは下記のコラムで解説しているので是非ご確認ください。
【2025年最新】車通勤の通勤手当の基準と計算式は?通勤手当管理者が知るべき支給条件
それぞれの方法にメリットとデメリットがあるので、どの方法が自社に合っているかを確認して選択しましょう。
また、自動車・バイク通勤を認める場合は、従業員に免許証や任意保険証、車検証などの書類をコピーして提出してもらう企業が多いです。
従業員が万が一通勤途中で事故を起こしたり、免許が切れた状態で運転していることが発覚した場合は、その交通手段での通勤を認めていた企業側も責任を問われる可能性があります。証明書のコピーの提出は、通勤経路申請時の一度だけでなく、期限が切れる前に新しい証明書のコピーを再提出する仕組みを作ることも重要です。
自転車通勤を認める場合の決め方
自転車通勤は、駐輪場代以外にかかる費用がありません。企業によっては駐輪場代や一律金額の支給をしているところもありますが、自転車通勤者には通勤手当を支給しないという企業も多いです。
自転車通勤者に通勤手当を支給する場合は、2キロ以上の距離であれば非課税での支給が可能になるため、走行距離の確認や非課税限度額を意識した金額の設定が必要になります。
また、自転車通勤も事故を起こす可能性があるため、任意保険の加入を義務化して証明書のコピーの提出と期限管理を行うことをおすすめします。
通勤手当の支給対象距離の測り方
適正な通勤手当を支給するために欠かせないのが通勤距離の計測です。
非課税限度額内で通勤手当を支給したい場合に気を付けるべきことを交えながら距離の計測方法をご紹介します。
直線距離と道なり距離、どちらで計算したらいい?
距離には、自宅から勤務地を直線で結んだ「直線距離」と、自宅から勤務地に通勤する際に実際に通る道の「道なり距離」の2種類あります。
繰り返しになりますが、通勤手当の計算には法的なルールが存在しないためどちらの距離を用いて計算しても問題はありません。
ただし、自動車・バイク・自転車通勤の通勤手当は、「道なり距離」に応じた非課税限度額が設定されているため、「道なり距離」の計測は必須です。そのため、計算にも「道なり距離」を用いる企業が多いです。
参考:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
2キロ未満の場合は支給しなくていいのか
自動車・バイク・自転車通勤の通勤手当は、2キロ未満の場合全額課税になります。
そのため、通勤経路が2キロ未満の従業員には通勤手当を支給しない企業も多いです。
ただし、電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合の通勤手当には距離による非課税限度額の条件がないため、「経済的かつ合理的な経路」であれば2キロ未満の距離でも非課税で支給することが可能です。
また、「自宅から駅までは自動車、駅から勤務地までは電車」のように交通手段が混在している場合の非課税限度額の扱いは以下のようになります。
|
電車やバスなどの交通機関のほか、併せてマイカーや自転車なども使って通勤している場合
この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。 (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
引用: 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」 |
通勤手当を支給する際の注意点
ここまで通勤手当の決め方を解説してきましたが、通勤手当を適正に支給するうえで特に気を付けるべき点についてもご紹介します。
パート・アルバイトも正社員と同じ支給額にする
通勤手当を扱われている皆様ならご存知かと思いますが、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、雇用形態の違いを理由に待遇差をつけることは認められていません。
これは通勤手当にも当てはまり、厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」で通勤手当について同一の支給を行わなければならないと明記されています。
例えば、「アルバイトは通勤にかかる交通費の半額相当のみを支給するが、正社員は全額相当を支給する」ということは認められません。
不正受給が起こりにくい仕組みを整える
通勤手当の不正受給は、故意に行われるものだけでなく、認識不足や申請忘れによって意図せず引き起こされる場合もあります。
故意に行われるものは、通勤経路を申請する際にわざと遠回りで高額な経路を提出したり、通勤手当を受給しておきながら徒歩や自転車で通勤したりするケースがあります。
対策としては、地図や乗換案内を用いて申請された経路を検索し、自社の規定に合っているかと、より経済的かつ合理的な経路がないかの確認を行うことが有効です。
認識不足や申請忘れを防ぐには、自社の規定の周知徹底が必要になります。
悪質な不正受給については、受け取っていた手当の全額返還要請と懲戒解雇処分を下された例や、裁判になった例もありますので、不正受給が起こりにくい仕組みを整えることが大切です。
通勤手当は社会保険料の対象
通勤手当は社会保険料の計算対象です。
社会保険料を算出するために必要な「標準報酬月額」は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を算出する際に基準となる金額です。
社会保険料計算の元となる通勤手当の金額が違うと標準報酬月額も変わってしまうため、通勤手当の管理は正確に行う必要があります。
標準報酬月額を誤って提出した場合には、従業員の給与や将来受け取る年金額に影響が出たり、企業に罰則が科せられたりするため正確な管理を心がけましょう。
通勤手当が非課税になる範囲を確認する
「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で支給する通勤手当は、条件を満たせば一定額まで非課税になります。非課税限度額は、交通手段や距離によって異なりますので、支給する際は非課税になる条件をしっかりと確認しましょう。
電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合は、1ヶ月当たりの非課税限度額は15万です。自動車・バイク・自転車などの交通用具を利用する場合は、下表のとおり通勤距離に応じて非課税限度額が変動します。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表(2025年12月更新)
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2キロ 未満 | (全額課税) |
| 2キロ 以上 10キロ 未満 | 4,200円 |
| 10キロ 以上 15キロ 未満 | 7,300円 |
| 15キロ 以上 25キロ 未満 | 13,500円 |
| 25キロ 以上 35キロ 未満 | 19,700円 |
| 35キロ 以上 45キロ 未満 | 25,900円 |
| 45キロ 以上 55キロ 未満 | 32,300円 |
| 55キロ 以上 | 38,700円 |
参照:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
有料道路の料金等も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当すれば非課税の通勤手当に含まれます。
非課税限度額を超えた分は課税対象になります。
通勤手当の申請は「らくらく通勤費」
通勤手当の支給は、注意するべきことが多く、正確に行おうとすると非常に手間のかかる業務です。また、お金にかかわることなので不公平感があると従業員の不満が生まれやすく、ミスによって税務調査のリスクもあるため管理担当者は大きなプレッシャーを感じているのではないでしょうか。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」なら、社内規定に合わせて通勤経路を表示するので、通勤手当の申請・承認・経路チェック時の手間を大幅に削減します。規定外の経路を表示しないことで、故意による不正受給を防ぐこともできます。
また、支給額の計算や、払戻し計算、課税・社会保険計算を自動化することができ、免許証や任意保険証などの証明書の画像と期限を管理することもできます。
業務効率化や適正な支給のために一度システム化の検討をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
通勤手当は労働基準法に規定はなく企業に支給義務はありませんが、多くの企業が福利厚生として支給しています。一般的には非課税限度額の範囲内で「経済的かつ合理的な経路および方法」での支給をされています。
正社員・非正規社員間での待遇差は禁止されているので、全従業員同一のルールで支給する必要があります。また、不正受給が起きにくい仕組みの整備や、社会保険料計算や非課税限度額の理解も必要です。
業務効率化や適正な支給には、システム化がおすすめです。
工数を削減したい、適正な支給をしたい、ミスを防止したいなどの課題をお持ちでしたら是非ご一考ください。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。