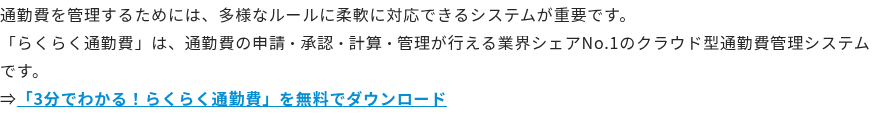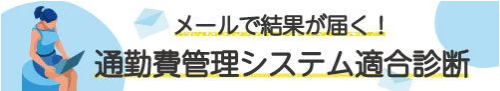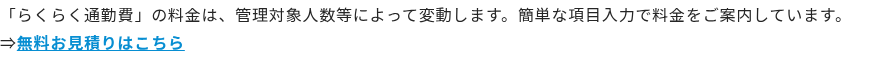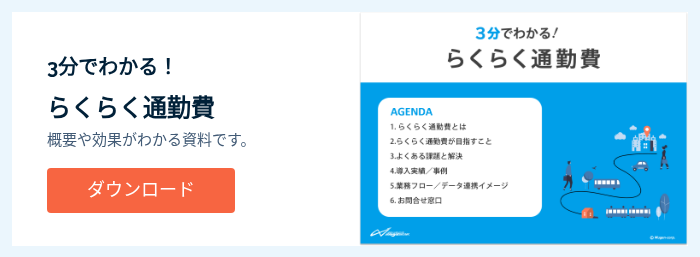【2025年最新】車通勤の通勤手当の基準と計算式は?通勤手当管理者が知るべき支給条件
監修者:佐川豊
この記事の目次

また、支給方法によっては従業員の不満がたまりやすい点も管理担当者を悩ませるポイントです。
今回は、車通勤の通勤手当の基準や計算式と、通勤手当管理者が知るべき支給条件について解説します。
車通勤の場合は通勤手当が一定額まで非課税になる
まずは、車通勤の通勤手当計算について考える際、最低限知っておきたい非課税限度額について説明します。
走行距離によって変わる「車・自転車通勤者の非課税限度額」
通勤手当における非課税限度額とは、所得税の課税対象とならずに支給できる通勤手当の上限額を指します。
例えば、月収20万円の従業員に対して毎月1万円の通勤手当を支給する場合、月収は総額21万円になります。しかし、支給される通勤手当が非課税限度額以下なら、所得税の税額計算の対象になるのは、月収20万円の部分のみとなります。
公共交通機関を利用する通勤手当の非課税限度額は、距離に関わらず一律金額です。
しかし、車や自転車等の交通用具を利用する通勤手当の非課税限度額は、走行距離によって変動するので注意が必要です。
非課税となる通勤手当の上限額はどのように計算される?
非課税限度額を確認する前に、前提の確認です。
通勤手当が非課税として認められるのは、その通勤方法と経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合に限ります。通勤手当を支給する際は、予め通勤方法や経路についても確認してください。
「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合は、下表のように片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
マイカーなど交通用具で通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額の表(2025年12月更新)
| 片道の通勤距離 | 1ヶ月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2km 未満 | (全額課税) |
| 2km 以上 10km 未満 | 4,200円 |
| 10km 以上 15km 未満 | 7,300円 |
| 15km 以上 25km 未満 | 13,500円 |
| 25km 以上 35km 未満 | 19,700円 |
| 35km 以上 45km 未満 | 25,900円 |
| 45km 以上 55km 未満 | 32,300円 |
| 55km 以上 | 38,700円 |
参照:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
また、「自宅から駅までは車、駅から会社までは電車」のように車と公共交通機関を併せて利用している場合には、車通勤の上表の通勤距離に応じた非課税限度額と、公共交通機関利用の1ヶ月間の通勤手当の合計が、1ヶ月当たり15万円までであれば課税されません。
車通勤の通勤手当が課税対象となるケースとは?
非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超えた部分の金額が課税対象になります。
例えば、2km以上10km未満の非課税限度額は4,200円ですが、5,000円を支給する場合は、非課税限度額を超えた800円が課税対象となります。
この超えた金額は、通勤手当を支給した月の給与額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
また、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当しない通勤手当や、個人名義で借りている駐車場代を支給する場合は課税対象になります。
車通勤の通勤手当支給には一律支給、距離別支給などがある
車通勤の通勤手当の計算方法は、主に以下の3種類があります。
・距離に関係なく一律金額を支給する方法
・距離区間ごとに支給額を決めて支給する方法
・距離とガソリン単価や燃費を使用して計算する方法
距離に関係なく一律金額を支給する
一番簡単な支給方法は、距離に関わらず車通勤している従業員全員に同じ金額を通勤手当として支給する方法です。しかし、このやり方では会社の近くに住んでいる従業員と遠くに住んでいる従業員との間に待遇差が出てしまうため、一番従業員からの不満があがりやすい方法でもあります。
一律金額支給方式のメリットとデメリット
■メリット
・従業員ごとの計算が不要
・通勤手当におけるコスト見通しが立てやすい
■デメリット
・実際の距離に関係なく支給するため公平性に欠ける
・公平性に欠けることや、遠くに住む従業員の支給額は実際にかかる金額よりも大幅に低くなりやすいことにより従業員が不満を感じやすくなる
一律金額支給する場合も「最も経済的かつ合理的な経路」に該当するかの確認と、片道の走行距離が2km以上であるかの確認は必要です。
距離区間ごとに支給額を決めて支給する
一律金額の支給よりも公平で従業員の不満が出にくい方法として、非課税限度額に合わせるなどして距離区間を設け、区間ごとに支給額を決めて支給する方法があります。
例)
片道距離が 2km以上 10km未満の場合 一律4,200円を支給
片道距離が10km以上 15km未満の場合 一律7,300円を支給
この方法では片道の通勤距離によって1ヶ月分の支給額が決まるので、一律金額の支給よりも管理の手間はやや上がります。
距離区分ごとに支給額決定方式のメリットとデメリット
■メリット
・一律金額支給よりも公平で比較的不満が出にくい
・非課税限度額に合わせて支給額を設定する場合は、課税・非課税の判断が不要
・計算が不要
■デメリット
・一律金額支給よりは公平であるものの、同じ区分内では不公平がある
距離とガソリン単価や燃費を使用して計算する方法
多くの企業で採用されている方法は、距離とガソリン単価や燃費を使用して計算する方法です。
この方法の中にも大きく分けて2通りあり、1km当たりの単価を決めて行う計算と、ガソリン単価と燃費の基準値を決めて行う計算があります。通勤手当は支給義務がなく、企業が自由にルール化できるものなのでどちらの計算式を選んでも問題ありません。
距離とガソリン単価や燃費を使用した計算式
1km当たりの単価を20円や30円などと決めて行う計算式
片道距離×2(往復)×km単価(〇〇円)×出勤日数(または所定労働日数)
ガソリン単価と燃費の基準値を決めて行う計算式
片道距離×2(往復)×ガソリン単価÷燃費×出勤日数(または所定労働日数)
ガソリン単価をいくらに設定するか基準に迷う場合は、資源エネルギー庁が小売価格の調査結果を発表しているので、こちらを参考にするのがおすすめです。
車種ごとの燃費の平均値は、国土交通省のホームページで確認することができます。
距離とガソリン単価や燃費を使用した支給方式のメリットとデメリット
■メリット
・一番公平な方法で不満が出にくい
・計算式に根拠があり、支給に対して納得感を得やすい
■デメリット
・計算が必要
・ガソリン価格高騰の際などは単価を変更して再計算が必要になることもある
一律支給と距離別支給の比較表
車通勤の通勤手当の支給方法別のメリット、デメリットを表にまとめると以下のようになります。
| 公平性 | 従業員の納得感 | 計算の難易度 | 管理の手間 | |
| 距離に関係なく一律金額を支給 | × | × | ○ | △ |
| 距離区間ごとに支給額を決めて支給 | △ | △ | ○ | △ |
| 距離とガソリン単価や燃費を使用して計算 | ○ | ○ | × | × |
公平性と従業員の納得感を取るか、計算の難易度と管理の手間が軽い方を取るか悩ましい問題です。
近年では、従業員が他社の支給についての情報を集めやすい分、他社に比べて通勤手当の計算が細かく行われないことへの不満があがりやすくなっています。
通勤費管理システムを導入すると、以下のような計算と管理の手間を大幅に削減できるので、公平性と従業員の納得感を得ながら管理者の負担を軽くすることもできます。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」でできること
・通勤経路の妥当性チェック
・自宅住所から勤務地の距離計測
・計算式の設定、自動計算
・ガソリン価格変動時の一括再計算
・各種証明書の提出、期限切れチェック
高速道路料金・駐車場代の取り扱い
企業によっては高速道路料金や駐車場代を支給している場合もあります。
通勤における高速道路料金や駐車場代は、企業側に支給義務がないため自由にルール化できます。
高速道路料金は、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」と判断できれば、15万円まで非課税として認められますが、理由なく高速道路を使用する場合は非課税と認められません。
駐車場代は個人名義で借りている駐車場代を支給する場合は課税対象になります。会社名義の契約で会社が支払う場合は従業員の給与所得の対象にはなりません。
車通勤の通勤手当精算を行う場合の注意点
車通勤の通勤手当精算を行う場合は、計算方法や条件をあらかじめルール化しましょう。ルールを決める際は、非課税限度額を超える場合の取り扱いについても考える必要があります。
通勤手当について就業規則等でルールを決めておく
社内に一定のルールがないと、管理担当者ごとや拠点ごとに通勤手当の計算方法が異なり、従業員の待遇に差が生じる恐れがあります。そのような事態を避けるために、就業規則や通勤規程でしっかりとルールを決めておきましょう。
車通勤者の通勤経路確認はどこまで必要?
非課税限度額の要件を満たすためには「最も経済的かつ合理的な経路」であるかの確認が必要です。
確認方法は企業によってまちまちですが、地図ソフトでの経路検索や、車のメーター読みで従業員から走行距離を提出してもらい、管理者側でも地図ソフトなどを使用して大きなズレがないか確認するのが一般的です。
地図ソフトや車のメーター読みは、使用する地図ソフトや車が同一でないと、計測する距離に差が生じてしまいます。公平に計測するために、申請者と管理者の双方で同一の地図ソフトを使用するルールの企業もあります。
経路の確認方法についての決まりはありませんが、合理的理由のない遠回りな経路を認めないように工夫をしましょう。
車通勤の通勤手当規定作成時のチェックポイント
通勤手当規定を作成する際は、以下の内容を従業員目線と管理者目線の両方で検討すると決めやすいです。
・車通勤者に通勤手当を支給するか、高速道路料金と駐車場代を支給するか
・支給サイクル(毎月、6ヶ月毎など)
・「最も経済的かつ合理的な経路」を満たすための基準
・「最も経済的かつ合理的な経路」の確認方法
・計算、支給方法を決める際に重視すること(公平さ、管理工数など)
・提出書類と、免許証や任意保険証の期限管理方法
・運用手段(紙、Excel、システムなど)
ルールを新しく設定する際やルールの見直しをする際は、通勤費管理システムベンダーにシステム化の相談をすると、自社に似た条件の他社事例を交えて説明してもらえるのでおすすめです。
公平性を確保するための基準設定
給与・手当の支給において公平性を確保することは、従業員の不満を減らし納得感を得ることに繋がるので、とても大事です。公平性を従業員に示すために様々な企業で実際に行われている工夫をご紹介します。
・距離測定は、申請者も管理者も同一地図ソフトを使用する
・車種(軽/普通/ハイブリッド等)ごとに燃費を設定し、計算式に組み込む
・ガソリン単価を都道府県ごとに設定し、毎月更新
定期的な見直しの必要性
通勤手当規定は、内容を決定する際にあらゆるケースを想定して作成しますが、法令や環境の変化で実態にそぐわなくなることもあります。通勤手当の支給について従業員からの問い合わせが増えたり、管理者が負担を感じたりする場合はすぐに見直しましょう。
目に見える問題がない場合でも、声をあげられていないだけで実は不満が募っているケースもあるので定期的に見直すことをおすすめします。特に法改正、ガソリン価格変動、道路状況の変化などがあった際は見直しのタイミングです。
車通勤者の通勤手当精算方法
通勤手当の精算方法は、企業によって異なります。
一口に「毎月1ヶ月分の通勤手当を支給」と言っても、月ごとに出勤日数を申請してもらい日数に応じた金額を支給する企業もあれば、申請させずに管理者が勤怠情報をもとに計算する企業や、毎月同じ固定額を支給する企業もあります。
いずれの方法でも問題ないので、自社にあったやり方を設定しましょう。
非課税限度額を超えると従業員の納税額が高くなる
通勤手当の金額が非課税限度額を越えると、従業員が納める所得税が増えます。
税金は生活を豊かにするために必要なものですが、個人的な意識でいえば「あまり多く払いたくない」と考える人も多いでしょう。
また、管理面では非課税限度額を超えた分は課税対象としての処理が必要になります。
対策として、通勤手当は非課税限度額を越えないように調整して支給する方法や、システム化をして課税・非課税の判断を自動化する方法があるので、どちらが会社や従業員にとってどちらが望ましいか検討しましょう。
複雑な車通勤の通勤手当計算はシステムを使って効率化しよう
今回は車通勤の通勤手当について解説しました。
公平な支給をするには手間が大きい車通勤の通勤手当支給ですが、システム化すると驚くほど簡単に公正な支給を実現できます。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」なら、適正な通勤経路の申請・チェックから、規定に合わせた柔軟な支給計算式の設定、課税・非課税額の判断、ガソリン価格変更時の一括再計算、証明書の管理など通勤手当に関する業務全体をカバーしています。
管理業務の省力化や、支給の適正化、従業員の満足度向上などの効果があります。
電車、バス、自転車、その他の交通手段にも対応しています。
通勤手当の管理をご担当されている方は、是非一度貴社の運用に合わせた説明を受けてみてはいかがでしょうか。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。