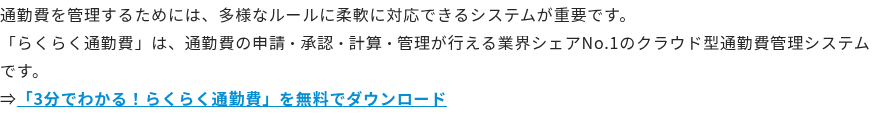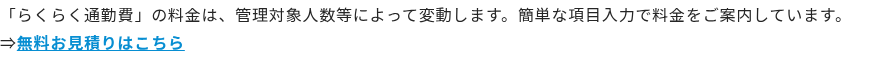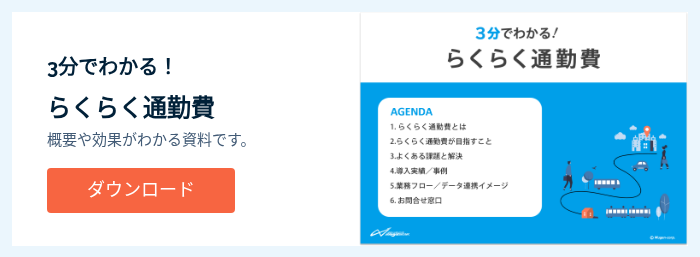マイカー通勤におけるガソリン代の計算方法について解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
マイカー通勤を認めている企業では、通勤手当としてガソリン代支給するケースが多いです。しかし、ガソリン代の算出方法や注意点を正しく理解していないと、従業員への支給額に誤りが生じる可能性があります。
本記事では、ガソリン代の計算方法を、ガソリン代計算に必要な走行距離や燃費の求め方から解説します。さらに、3種類の支給方法についてもまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
通勤手当におけるガソリン代の計算方法
マイカー通勤の場合、通勤にかかるガソリン代を計算して支給する企業が多いです。基本的な計算は走行距離・燃費・ガソリン単価を基に行います。これらを正確に把握することで、合理的な支給額を算出できます。
走行距離
走行距離は、自宅から勤務先までの道なり距離を指します。
計測の仕方で一般的なのは、地図サービスを利用して最短経路を確認するやり方や、自動車で自宅から勤務地まで走行した際のメーターの数値差から距離を計測するやり方です。
メーターの数値差で距離を計測して従業員本人に申請してもらう場合は、その距離が実態と大きくズレていないかを確認する必要があります。多くの企業では地図サービスを用いて確認を行っています。
片道の走行距離を計測できたら、1日分(往復分)の通勤距離を求めるために走行距離を2倍にします。
例えば、自宅から会社まで片道15kmの場合、往復で30kmとなります。
燃費
燃費とは、ガソリン1Lあたり何km走行できるのかを数値で表したものです。
燃費は車種により異なります。極端な例でいうと、ハイブリッド車等は1L当たり30km近くになることもある一方、スポーツカー等は1L当たり10kmを下回ることもあります。
燃費の数値は車のカタログに掲載されていますが、従業員一人一人の車を把握してそれぞれの燃費で通勤手当の計算をするのは現実的ではありません。
どの車種でも同じ燃費を設定する企業も多いですが、自動車は「普通車」や「大型車」などの大まかな車種で分けて燃費を設定したり、車と二輪車で分けて燃費を設定したりする企業もあります。
国土交通省のホームページでは車種ごとの燃費の平均値を確認できます。
燃費を計算する場合は、走行距離÷ガソリン消費量で求めます。
いずれの方法で燃費を設定する場合も、タイヤやオイルなど消耗品のメンテナンスが必要なことも考慮して、実際よりも少し悪い燃費を計算に用いる方が従業員の不満が出にくいでしょう。
ガソリン代
通勤手当におけるガソリン代は、走行距離÷燃費×ガソリン単価で計算します。
例えば、走行距離600km、燃費15km/L、ガソリン単価170円の場合の計算式は、600÷15×170=6,800となるので、ガソリン代は6,800円です。
ガソリン代を計算するときにガソリン単価をいくらに設定したらよいか基準に迷う企業も多いでしょう。
自社の近くにあるガソリンスタンドの価格を参考にする企業もありますが、資源エネルギー庁が定期的に発表している小売価格の調査結果を参考にするのもおすすめです。
ガソリン価格は常に変動するため、毎月・半年・1年などのサイクルで定期的な見直しが必要です。
通勤手当の支給方法
通勤手当の支給方法には、ガソリン代を計算して支給する方法の他にも選択肢があります。どの方法で支給しても法律上の問題はありませんが、計算の手間や従業員からの不満の出やすさに違いがあります。
全額支給
最も多くの企業で採用されている方法は、上で説明したような走行距離・燃費・ガソリン単価を使用して計算し、通勤にかかるガソリン代を全額支給する方法です。
全額支給の中にも大きく分けて2通りあり、上で説明した燃費とガソリン単価の基準値を決めて行う計算と、1km当たりの単価を決めて行う計算があります。通勤手当は支給義務がなく、企業が自由にルール化できるものなのでどちらの計算式を選んでも問題ありません。
一律支給
一番簡単な支給方法は、距離に関わらず車通勤をしている従業員全員に一律で同じ金額を通勤手当として支給する方法です。しかし、このやり方では会社の近くに住んでいる従業員と遠くに住んでいる従業員との間に待遇差が出てしまうため、一番従業員からの不満が出やすい方法ともいえます。
距離区間ごとの支給
一律金額の支給よりも公平で従業員の不満が出にくい方法として、非課税限度額に合わせるなどして距離区間を設け、区間ごとに支給額を決めて支給する方法があります。
例)
片道距離が 2km以上 10km未満の場合 一律4,200円を支給
片道距離が10km以上 15km未満の場合 一律7,300円を支給
この方法では片道の通勤距離によって1ヶ月分の支給額が決まるので、一律金額の支給よりも管理の手間はやや上がります。
また、「2km以上 10km未満」を同じ金額とした場合、通勤距離が2kmの従業員と9kmの従業員では2kmの従業員の方が得になりますので、全額支給に比べると従業員からの不満が出やすいです。
通勤手当の計算は「らくらく通勤費」
通勤手当の支給計算を手作業で公平・公正に行おうとすると大変な手間がかかり、ミスが起きやすくなります。そもそも給与計算の一部なのに、何故システム化していないのかと感じる担当者様も多いのではないでしょうか。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」なら、走行距離の計測から設定した計算式での計算、支給、管理までを全て行えます。通勤手当に関する業務全体をカバーしているので、Excelや紙管理、手計算などのアナログ処理を辞められます。
導入時には、社内規定や運用方法のヒアリングを行い、設定や使い方の説明を十分に行います。システムを使いこなせるか不安な方にもご安心いただけるサポート体制をご用意しています。
導入前のお客様に向けて無料のWebご説明も行っておりますので、お気軽にお申し込みください。
⇒Webご説明のご予約はこちら
まとめ
今回は、マイカー通勤におけるガソリン代の計算方法について解説しました。
マイカー通勤の通勤手当は、走行距離・燃費・ガソリン単価を基に計算します。基本式は「往復の走行距離÷燃費×ガソリン単価」です。
燃費は車種ごとに異なるため、車種を大まかな区分で分けて区分ごとの平均の燃費を設定することが一般的です。燃費やガソリン単価は、国土交通省や資源エネルギー庁の公表値を参考にするのがおすすめです。
従業員の不満が出にくい方法は、ガソリン代を計算して全額支給する方法で、ガソリン単価は価格変動に応じて定期的に見直すとよいでしょう。
また、通勤費管理の省力化や公正化に興味がある方は、ぜひ「らくらく通勤費」の導入をご検討ください。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。