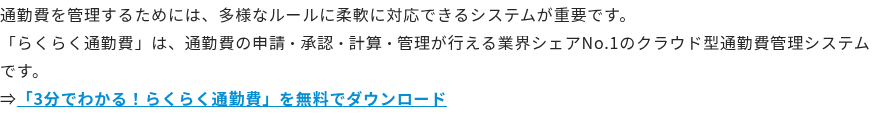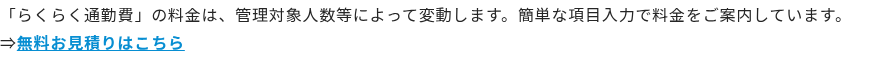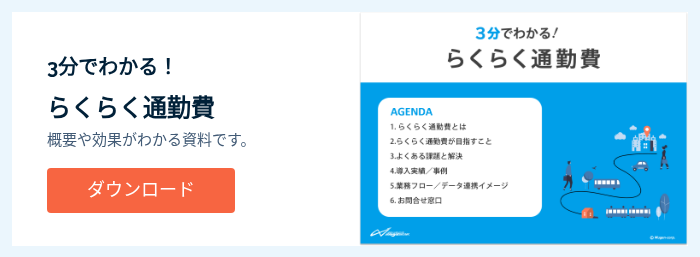通勤手当の実費支給とは?定期代支給と実費支給の比較や、交通手段ごとの計算方法を解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
定期代の支給を廃止して、通勤手当を実費支給に切り替えている企業が少なくありません。
一方で、実費支給への切り替えはどのような問題があるかわからないが、業務処理が煩雑になりそうなので二の足を踏んでいる、という声も耳にします。
通勤手当の実費支給とは
通勤手当の実費支給とは、従業員が出社した日数に応じて実際に負担した運賃やガソリン代を後払いで精算する方法です。
鉄道の1ヶ月定期券代をきっぷ代に換算すると16~19日分の往復料金相当になります。出社日数がそれよりも少なければ実費支給にした方が企業にとってコストの抑制になります。
非課税限度額と社会保険料計算の考え方は定期代支給と同じです。
1ヶ月当たりの「経済的かつ合理的な」経路を使用した通勤手当を対象として非課税の限度額が定められています。公共交通機関であれば月額15万円まで、マイカー・自転車等の交通用具でしたら距離区分に応じて月額最大38,700円まで非課税となります。
社会保険料については、通勤手当として支給した金額が計算対象になります。
実費支給が増えた背景には、新型コロナ対策や働き方改革によるテレワーク導入の拡大があります。それまで通勤手当の実費支給対象はパートやアルバイトが中心でしたが、テレワークの増加とともに正社員への実費支給も増加しました。
現在は、「部署ごとや人ごとに定期代支給と実費支給のお得な方を判断して支給する」という企業も増えています。
実費支給と定期代支給の比較
通勤手当の定期代支給から実費支給への切り替えは、会社が負担するコストの抑制になりますが、ほかにどのような影響があるのか、比較を以下にまとめてみました。
| 実費支給 | 定期代支給 | |
| 企業が負担するコスト | 小さい | 大きい |
| 支給方法 | 後払い(毎月精算) |
当月払い 先払い(1・3・6ヶ月の期間で支給) |
| 従業員のメリット | 異動時の払戻し計算が発生しない | 更新が楽、定期区間内の利用が自由 |
| 従業員のデメリット | 毎月申請が必要 | 変更時に払い戻し計算が発生 |
| 向いている企業 | テレワーク導入企業、パートアルバイトが多い、通勤先が複数の企業 | 常時(週5日)出社が必要な業務形態 |
1ヶ月当たりの出社日数が少なければ、1ヶ月定期代支給より実費支給の方がコストメリットがあります。常時出社の場合には、6ヶ月定期券などの長期の定期券の方が割引額が大きいのでメリットがあります。定期代支給では毎月の申請とその確認が不要になるので、従業員と業務担当者の業務工数を抑えることが出来ます。
実費と定期券の金額比較を試算してみました。(2025年8月時点の料金)
例えば、通勤区間が立川~新宿の場合の運賃は以下となります。
片道運賃 483円 往復運賃 966円
1ヶ月定期 14,640円
3ヶ月定期 41,720円
6ヶ月定期 70,350円
1ヶ月定期代(14,640円)÷往復運賃(966円)=約16日分となります。
出社日数が16日を超えない場合は、実費支給の方が安くなります。
3ヶ月、6ヶ月先の出社日数が計算できる場合は、3ヶ月や6ヶ月定期券と実費を比較することもできるでしょう。
3ヶ月・6ヶ月定期と往復運賃の比較は以下となります。
3ヶ月定期代(41,720円)÷往復運賃(966円)=43.2日分
6ヶ月定期代(70,350円)÷往復運賃(966円)=72.8日分
テレワーク率の高い企業や、パートアルバイトが多く出社日数の変動が大きい企業は実費支給向きと言えます。常時出社が必要な企業は、定期代支給の方が適していると考えられます。従業員の働き方に応じてテレワークも常時出社も認めている企業は、実費支給と定期代支給の両方に対応する必要があります。
さらに広がりそうな、通勤手当の実費支給
新型コロナ対策で、急速に導入が進んだテレワーク。それによって従業員の出社日数が減少したことから、より小規模なオフィスへ移転したり、定期代の支給を廃止して通勤手当の実費支給に切り替えたりする会社が増えていることを、以前のコラムでご紹介しています。
テレワークの導入、オフィス移転、通勤手当の実費支給への切り替えはいずれも経費節約のメリットがあり、経営上合理的な判断といえるでしょう。
このうち通勤手当の実費支給への切り替えは、大きな設備投資などもなく比較的取り組みやすいことから今後もさらに拡大していくと考えられます。
通勤手当の実費支給額の計算方法
通勤手当の実費支給での計算方法を交通手段別に解説します。
前提としてどのような交通手段においても、「経済的かつ合理的」と認められる経路でなければなりません。
出社日数は、勤務表やタイムカード、勤怠システム等で客観的に確認できる必要があります。
①公共交通機関(鉄道・バス)
片道運賃×2(往復)×出社日数
ただし、バス利用条件や利用する駅(自宅最寄駅、勤務地最寄駅)が就業規則等に則っていることが条件となります。その上で利用経路が「経済的かつ合理的」かどうか判断し、片道運賃を求めます。
②自家用車・バイク(交通用具)
片道距離×2(往復)×距離単価×出社日数
または
片道距離×2(往復)×ガソリン単価×燃費×出社日数
自宅から勤務地までの距離を正しく計測し把握する必要があります。
③自転車・徒歩
2km未満の場合0円
2km以上の場合、片道距離×2(往復)×単価×出社日数
または
2km以上の場合、月額〇〇円
自家用車・バイク同様距離は正しく計測し把握する必要があります。
実費支給計算時は以下の点も注意が必要です。
・「経済的かつ合理的」な経路でない場合は、課税通勤費となる
・「最短かつ最安」でない経路を認める場合の判断基準を定めておく
・交通用具の非課税限度額の上限は38,700円。定期代相当額を支給している場合課税通勤費が発生することがある
・交通用具利用かつ有料道路利用の場合、または交通用具利用かつ鉄道・バスなどの公共交通機関を併用の場合は非課税限度額は15万円
・勤務地の変更や転居による住所変更の際は、距離の再計測が必要
公共交通機関(鉄道・バス)利用時の計算方法
・公共交通機関の計算方法:
片道運賃×2(往復)×出社日数
通勤経路は「経済的かつ合理的」で就業規則等のルールに則っているものが認められます。
きっぷ料金では10円単位、ICカード料金では1円単位の金額となっていますので、あらかじめどちらの料金を採用するか決めておく必要があります。
ICカードの場合は、履歴を印刷したり、モバイルSuicaやモバイルPASMOのアプリで確認することもできます。
システムでICカードの利用履歴から通勤利用分だけ計算できると便利です。
通勤経路は、「経済的かつ合理的」な経路の判断が必要です。「時間がかかるが安い」、「最安ではないが早い」経路などは、例えば「最安から30%までの金額を認める」、「最安経路よりも15分以上短縮できる経路の場合は認める」など、金額と時間の合理的な判断基準を規定し判断します。
また、長距離通勤で新幹線や特急を利用する場合についても「合理的」な判断基準を規定する必要があります。
これらに基づいて、正しい計算を行いましょう。
自家用車・バイク通勤の計算方法
・距離単価による計算方法:
片道距離×2(往復)×距離単価×出社日数
例)片道10km・単価20円・15日
⇒ 10km×2(往復)×20円×15日=6,000円
※距離単価は、15~25円/kmが多いようです
・ガソリン単価と燃費による計算方法:
片道距離×2(往復)×ガソリン単価×燃費×出社日数
例)片道10km・ガソリン単価180円/l・燃費10km/l・15日
⇒10km×2(往復)×(180円÷10 km)×15日=5,400円
距離の計測方法は、インターネットの地図や紙の地図による計測、車やバイクのメーターによる計測などがあります。
申請方法や計測方法により差や不正が発生しないよう、客観的に距離を把握できる方法が望ましいでしょう。
関連記事:車通勤の通勤手当の基準と計算式は?通勤手当管理者が知るべき支給条件
車通勤における駐車場代の取り扱い
駐車場の利用は課税通勤費が発生する場合があるので、駐車場代の取り扱いには注意が必要です。
会社が契約している駐車場を利用させる場合は、会社の経費(地代家賃、賃借料など)となり通勤手当に含まず、課税通勤費にはなりません。しかし、従業員が駐車場を個人契約し、駐車場代を通勤手当に含んで支給する場合は、駐車場代の金額について全額課税となります。
所得税法では、非課税とされる通勤手当に「自動車その他の交通用具」や「運賃等」とあり、駐車場代が含まれていないので課税となります。
個人契約の駐車場の場合、駐車場代に差があることが考えられますので、支給上限を月額5,000円とし超過分は自己負担とするケースもあります。
自転車・徒歩通勤者への実費支給
自転車通勤の場合は、自家用車・バイクと同様に交通用具となり、距離による非課税限度額が定められています。
片道距離が2km未満は全額課税通勤費となるため、2km 未満には通勤手当を支給しない企業が多いです。
自転車通勤の場合の実費支給計算としては、距離に応じて支給する場合や一定金額の支給があります。
・距離に応じた支給金額:
2km未満の場合0円
2km以上の場合、片道距離×2(往復)×単価×出社日数
例)片道3km・単価50円・15日
⇒ 3km×2(往復)×50円×15日=4,500円
・一定金額(日額)の支給:
片道2km以上の場合、日額100円
・一定金額(月額)の支給:
片道2km以上の場合、月額2,000円
距離区分で2~10km、10~15km、15~25kmの場合で支給金額を定めているというケースもあります。
距離の計測方法は、インターネットの地図や紙の地図による計測が一般的です。
申請方法や計測方法により差や不正が発生しないよう、客観的に距離を把握できる方法が望ましいでしょう。
徒歩通勤の場合、距離にかかわらず支給しないのが一般的です。
実費支給で通勤手当コストは減った、でも業務量は?
実費支給の一般的なやり方
出社日数に応じた実費支給はほとんどの会社で事後精算としています。具体的には、交通機関を利用する際に従業員が運賃を立て替えて支払っておき、事後に従業員が個別で実費を申請。人事総務部門などの通勤手当担当者が処理して、翌月の給与と共に従業員へ支払う方法です。
これだけ見れば、簡単に処理でき問題なさそうです。しかし、実際に運用を始めると、管理部門の業務量が増え残業時間が大幅に増加したという話も聞きます。
では、どのような作業をしているのか見てみましょう。
通勤手当の実費支給における担当者の業務
・申請者(従業員)の、実際の出社(通勤)日数を確認し、申請書と照合
↓
・申請者(従業員)の、通勤ルートおよび運賃の確認
(定期券利用時の経路と異なる場合は、その妥当性もチェック)
↓
・ 運賃と出社日数から総額を計算、申請書と照合
↓
・責任者の承認を取った上で、給与システム等へ反映
これを実費支給の従業員全員に対して行うため、業務の手間が膨大になります。
定期代の支給のみであれば、数ヶ月に1度の更新作業で済んでいたものが、実費支給では毎月作業が発生します。 実費支給にしたことにより管理部門の残業時間が急激に増え、労働環境が悪化したという話は少なくありません。
例外的な通勤手当の実費支給方法とその課題
会社によっては定期代の支給と実費支給が併存している場合もあります。
その場合には実費支給申請の処理を毎月行いながら、以下の作業も実行しなければなりません。
・定期代の支給手続き

そして、従業員ごとの通勤日数によって「実費通勤費」と「1ヶ月定期代」を比較し、安価な方を支給している会社もあります。
「実費通勤費」と「1ヶ月定期代」の金額の確認業務が発生し、管理担当者の大変さが伺われます。
さらに別の側面から見れば、申請者(従業員)も自分が通勤した日を記録しておき、毎月通勤回数を計算して申請する手間(時間)をかけています。定期代を支給していた頃には無かった業務であり、それを全従業員が行っているとなれば、目に見えない形で時間を使い、以前よりも多大な人件費が発生していることになります。
通勤手当の課税・非課税について
所得税法では、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も「経済的かつ合理的」な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額に対し非課税限度額を定めています。
公共交通機関であれば月額15万円まで、自家用車・自転車等の交通用具でしたら距離区分に応じて月額最大38,700円まで非課税の限度額となります。
「経済的かつ合理的」と判断できれば、新幹線や特急列車、有料道路等の利用を非課税と認められますが、グリーン料金は課税所得となります。
非課税限度額の詳細は、以下の表を参照してください。
| 区分 | 課税されない限度額 |
| 1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 最大38,700円 |
| 3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
| 区分 | 課税されない限度額 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満 | (全額課税) | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 | |
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,900円 | |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,300円 | |
| 通勤距離が片道55キロメートル以上 | 38,700円 |
参考:国税庁「電車・バス通勤者の通勤手当」「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
定期券の解約に絡んで注意したいこと
実費支給の導入の際、定期券の有効期限内に切り替える場合は、定期券の途中解約(払い戻し)手続きが発生します。そこで気を付けたいことが2つあります。
ムダの少ない定期券払い戻しを
1つは、解約のタイミングです。鉄道定期券の場合、解約は基本的に「月割計算」となります。このため利用開始日から1ヶ月ごとに区切りをつけており、定期券払い戻しは解約を処理した日の翌月(次の区切り)からとなるため、区切りを1日でも超えてしまうとさらに次の月からの定期券払い戻し(1ヶ月分)になってしまいます。
定期券払い戻しの例:4月10日利用開始の3ヶ月定期の場合

なお、定期券払い戻しがあった場合、多くの会社でその金額を当該従業員の解約月または翌月の給与から差し引いて(控除して)いますので、日付によっては1ヶ月分のズレが生じることがあります。
通勤手当の定期券代・実費精算は、社会保険料の算定に影響
もう1つは、社会保険料の計算です。
社会保険の標準報酬月額の算定には4~6月の通勤手当の実績が関わってきますが、この間に定期券の払い戻しをした場合、計算がより複雑になります。上記の定期券払い戻しの「月割計算」が再び絡んでくるからです。計算の考え方は、下記の通りです。

社会保険料は、将来の年金支給額にも関わってくるため、正確な算定・申告が求められます。定期券の払い戻しには、十分な注意が必要です。
関連記事:通勤費と交通費の違いとは?計算方法や支給時の注意点を解説
実費支給の運用方法と効率化
実費支給の運用を円滑に進めるためには、通勤経路の適正な確認、正確な情報管理、そして業務の仕組み化による効率化が重要です。
通勤手当の管理では、実費支給だけでなく定期代支給にも対応する必要があります。
実費支給では、出勤日数を取り込んだうえでの正確な計算が求められ、定期代支給では定期券の更新や払い戻しなどの管理も含まれます。
これらの業務をシステム化することで、毎月の申請作業を最小限に抑えられ、通勤経路の判定や金額の計算、情報の管理にかかる手間を大幅に削減できます。結果として、業務の効率化を実現するだけでなく、人的ミスの防止にもつながります。
実費支給業務の効率化ツール
通勤手当の実費支給業務を効率化するためには、通勤費管理に特化したシステムの導入が最適です。通勤費管理システム「らくらく通勤費」を利用することで、実費支給に必要な経路のチェックや金額計算方法、金額確認、定期代との比較などをスムーズに行うことが出来ます。
通勤手当のさまざまな課題は、システムで克服できる
通勤手当の定期代支給から実費支給への切り替えを中心に紹介しましたが、通勤手当には他にもさまざまな課題があります。以下のような課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
・転勤や異動、転居の際の定期代の払戻しや金額の確認、計算に手間がかかる
・鉄道会社やバス会社の運賃改定により、再申請や確認、計算が発生し時間がかかる
・様々な通勤方法や通勤手当の支払方法の運用が煩雑
・申請漏れによる遡り処理が大変
・Excelをはじめとする様々なツールを利用しないと管理できない
・業務が属人化しやすい
通勤費管理システム「らくらく通勤費」は、通勤手当の管理に特化しています。通勤手当の申請承認、計算、チェック、管理を「らくらく通勤費」ひとつで行うことができます。
勤怠システムや給与システムとの連携により、通勤手当の実費支給業務だけでなく、通勤手当管理全体の課題解決を実現することが可能です。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。