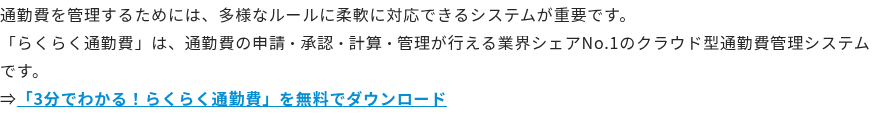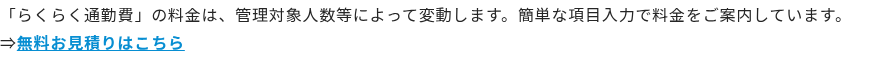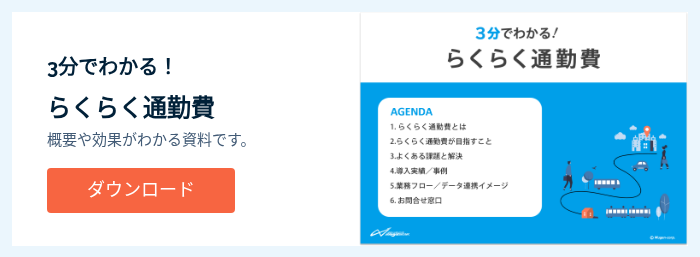通勤手当の計算方法って?課税ルールや支給時の注意点を解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
そもそも通勤手当とは?
通勤手当とは通勤交通費や通勤費ともいいます。
通勤手当は自宅から勤務地までの通勤のためにかかる費用の一部または全額を、福利厚生の一種として給与手当で支払われる交通費のことを指します。
通勤のためかかる費用には、鉄道やバスの定期代やきっぷ代(IC料金)、自動車(マイカー)・バイクのガソリン代や駐車場代、自転車の駐輪場代などが含まれます。
企業によっては、月額または日額の支給上限が定められている場合もあります。
マイカー・バイク・自転車による通勤手段に対しては通勤手当を支給しないという企業もあります。
交通費との違い
鉄道やバスなどの公共交通機関や、マイカーなどの移動手段は、通勤だけでなく業務で利用される方も多いでしょう。交通費という呼び方からも、通勤手当と交通費が混同されることも少なくありません。
同じ交通手段でも目的によって通勤手当か交通費かが異なります。
前述した通り、通勤のための交通費は通勤手当といい、給与での支給・計算対象となります。
そして、業務による移動に対して会社が支払う交通費や出張に対しては、「旅費交通費」「交通費」「出張費」となり経費で処理することとなります。
通勤手当=給与、交通費=経費と理解いただくと、目的と処理の違いが分かるかと思います。
企業は通勤手当を出さなくてはいけない?
通勤手当の支給について労働基準法には記載がなく、企業に支給義務がありません。通勤手当を出している企業は多いですが、出していない企業もあります。
基本給の中に通勤にかかる金額も含んで払い、通勤手当がないことも違法ではありません。むしろ海外では通勤費は自己負担が当たり前で、別途通勤手当が支給されることはありません。しかし、日本では慣習的に多くの企業が通勤手当を支給しています。通勤手当支給は日本的な賃金体系の特徴の一つと言えます。
通勤手当は、就業規則や賃金規程等に定めることで支給義務が生じます。そして多くの企業で、通勤手当の支給が規定されています。
通勤手当の対象となる通勤方法
就業規則等に定められた通勤方法が通勤手当の対象となります。主に通勤手当の対象となる通勤方法は以下が考えられます。
・鉄道(在来線、特急、新幹線等)
・バス
・フェリー等の船舶
・自動車(マイカー)
・バイク
・自転車
・徒歩
ただし、規程に定めていればどのような経路の通勤方法でも通勤手当の対象になるということでもありません。
「経済的かつ合理的」だと客観的に判断できる場合に、通勤手当支給の対象としているケースが多いでしょう。
企業によっては、自動車・バイク・自転車による通勤を認めていない場合もあります。
通勤手当の計算方法
通勤手当は交通手段によって手当の計算方法が異なりますが、いずれの場合も「経済的かつ合理的」かどうかを判断基準とします。
鉄道・バス、自動車(マイカー)、自転車・徒歩、タクシーの場合の計算方法をそれぞれ説明します。
鉄道・バスなどの公共交通機関の場合
鉄道・バスなどの公共交通機関では、定期代またはきっぷ代が「経済的かつ合理的」な経路かどうかを判断します。
バスの利用を認める条件として、従業員の自宅から最寄駅までの距離を定めます。
例えば、「直線1.5km以上」や「道なり距離2km以上」の場合にバスの利用を認める、などです。
鉄道では、自宅や勤務地付近の利用駅(最寄駅)を判定します。自宅・勤務地の最寄駅が複数ある場合がありますが、それぞれの経路を比較してどの経路が「経済的かつ合理的」かを判断します。
「経済的かつ合理的」を判断するために金額や時間の比較基準を規程に定める必要があります。例えば、「最安経路を第一の選択条件とするが、15分以上短縮できる経路があれば最安でなくても認める」といった具合です。
また、長距離通勤者の新幹線・特急通勤を認める条件なども定める必要があります。
それらの判断基準に基づいて、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月定期代や、出勤日数に応じたきっぷ代(IC料金)を計算して支給します。
自動車(マイカー)の場合
マイカー通勤の場合の通勤手当の計算方法は、主に以下の3種類あります。
・距離区間を設定し支給額を決める方法
・距離に応じた計算式を設定する方法
・一定金額を設定する方法
いずれの方法にしても、就業規則等に規定する必要があります。
距離区分を設定して支給額を決める方法
距離区分は非課税限度額に合わせて以下のように支給額を決めるケースがあります。
片道距離が2km以上10km未満の場合 4,200円
片道距離が10km以上15km未満の場合 7,300円 など
この場合は、片道距離によって1ヶ月分の金額が決められています。出勤日数が変動した場合については就業規則等で定めます。
距離に応じた計算方法
距離に応じた計算では、1km当たりの単価を決める計算方法と、ガソリン単価と燃費の基準値を定めて計算する方法があります。
1km当たりの単価を20円や30円などと決める計算方法です。
計算式の例としては以下の通りです。
片道距離×2(往復)×km単価(〇〇円)×出勤日数(または所定労働日数)
ガソリン単価と燃費の基準値を定めて計算する方法では、計算式の例としては以下の通りです。
片道距離×2(往復)×ガソリン単価÷燃費×出勤日数(または所定労働日数)
一定金額を設定する方法
通勤距離に関わらず、全社員一律月額5,000円や10,000円を支給する方法です。
支払金額が一定のため手続きが簡単に思えますが、自動車(マイカー)や自転車通勤に対する通勤手当には注意が必要です。
非課税限度額は片道距離によって異なるので、一定金額支給であっても距離の把握は必要です。
例えば片道距離が2km未満の場合は全額課税対象、10km未満の場合は4,200円を超える金額が課税対象となりますので、課税計算忘れが無いようにしなければなりません。距離に応じた非課税限度額は後段に記載します。
距離は直線距離や経路距離(道なり距離)として規定されます。距離計測については以下の計測方法がありますが、同じ経路でも計測方法による誤差が不公平感による不平不満につながる場合があるので注意が必要です。
・車のメーターで測る
・地図ソフトで計測する
・紙の地図に定規を当てて計測する
不公平の出ない基準を定めるとともに、その距離が「経済的かつ合理的」かどうかの判断が必要です。
ガソリン単価についても、以下のようにどのような価格を適用するか定めます。
・近隣のガソリンスタンドの価格の適用
・都道府県別の平均価格を適用
・全国平均価格を適用
そして、変動するガソリン価格の見直しタイミングを年数回にするのか、毎月にするのかなどを決めることも必要です。
関連記事 https://rk2.mugen-corp.jp/column/531
自転車・徒歩の場合
マイカーの場合と同様に距離計測方法を決め、距離を確認します。
自転車は2km未満だと全額課税対象となりますので、2km未満の場合は支給しないという企業も多いです。
自転車・徒歩の場合で通勤手当を支給する場合は1km当たりの単価を設定したり、月額または日額を設定しているケースがあります。
タクシーの場合
通常の出社に対しタクシー利用を認めている企業をほとんどないでしょう。ただし、交代勤務や緊急業務など深夜早朝で他に利用できる交通機関がない場合は、利用条件を限定し就業規則等に規定することで、タクシーによる通勤手当に支給を行うケースがあります。
通勤手当は課税される?
下記の表のように、通勤手当は一定の条件を満たしていれば、課税所得の対象外となります。金額や距離に加え「経済的かつ合理的」という基準のもと非課税を判断されます。
定期代などでは、1ヶ月当たり15万円が非課税です。新幹線通勤は妥当性があれば非課税と認められますが、グリーン料金は課税となります。また不必要に遠回りの経路と判断された場合も課税となります。
- 1ヶ月に支給される通勤手当が15万円を超えない場合
| 区分 | 課税されない限度額 |
| 1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 最大38,700円 |
| 3.交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度 150,000円) |
| 4.交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
- 上記2で以下の条件を満たす場合
| 区分 | 課税されない限度額 | |
| 通勤距離が片道2キロメートル未満 | (全額課税) | |
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 13,500円 | |
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,700円 | |
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 25,900円 | |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,300円 | |
| 通勤距離が片道55キロメートル以上 | 38,700円 |
参考:国税庁タックスアンサー「電車・バス通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

通勤手当の社会保険上の扱いとは?
通勤手当は非課税が認められていますが、社会保険については標準報酬月額の算定対象になります。社会保険算定では4・5・6月の各月の手当が計算対象となるので、3ヶ月定期や6ヶ月定期を支給している場合は、1ヶ月当たりの金額を算出し4・5・6月分として計算する必要があります。5月や6月に転居等で定期代が変わる場合は、1ヶ月当たりの金額が異なりますので、算定基礎の計算も注意が必要です。
雇用保険に関しても、1ヶ月分の通勤手当を算出する必要があるため、3ヶ月定期・6ヶ月定期を支給している場合は1ヶ月分を算出する必要があります。
通勤手当支給の注意点
テレワークなどの対応方法
テレワークや在宅勤務の場合は、出社時の交通費を通勤手当として出社日数に応じた実費を精算します。
テレワークや在宅勤務で、通勤手当の代わりに在宅勤務手当が支給された場合は、給与所得となるため非課税にはなりません。
雇用形態で差をつけない
同一労働同一賃金により、雇用形態(正社員・パート・アルバイト等)の違いで通勤手当の支給金額条件に差をつけることは認められません。通勤手当は業務上の役割や責任に関係ないためです。
ただし、出勤日数の違いや、利用する交通手段の違いによって金額の差が生じることは当然ですので、問題ないと考えられています。
就業規則で通勤規定を行う
通勤手当は企業に支給義務がないので、通勤手当の支給に関しては就業規則や通勤規程によって定めなければなりません。支給対象者や条件、金額を企業独自に定めることができますが、規程に則った運用が必要です。
変更時・廃止時は手続きを行う
通勤手当の支給方法の変更や手当の廃止をする場合には、就業規則や通勤規程の変更手続きが必要です。「労働条件の不利益変更」になるとして、支払を求められることもありますので、労働組合や従業員の合意を得て、就業規則や通勤規程の変更手続きを進める必要があります。
通勤手当制度を整備する際のポイント
通勤手当は企業に支給義務がありませんが、通勤手当を支給されている企業がほとんどです。
通勤手当制度の整備のために就業規則や通勤規程を定めるに当たっては、業務運用において従業員や担当者の申請・チェック・再計算などの負荷が大きくなりすぎないようにする必要があるでしょう。
給与の一部である通勤手当ですが、就業規則等に定めただけでは人事給与システムの機能で管理しきれない内容が多くあります。以下は通勤手当の管理業務でよくある課題です。
・「経済的かつ合理的な経路」判断の標準化
・不正な経路申請の防止
・バス利用の可否判断の簡略化
・距離計測の標準化
・複数の交通手段による通勤手当の計算
・転居、転勤、退職時の払い戻し計算
・鉄道・バスの運賃改定やガソリン単価変動への対応の効率化
・課税計算、社会保険計算の省力化
・申請忘れに対する遡り処理
このように、通勤手当は計算・確認・判断など手間が多く、現在通勤手当の管理を担当されている方も負担を感じているのではないでしょうか。
上記のような課題は、通勤費管理システムの「らくらく通勤費」で解決できます。
多様な通勤手当の規定に合わせた設定ができ、様々な人事給与システムとの連携も可能です。業務工数85%削減の実績がありますので、通勤手当制度の整備と併せてシステム化を検討いただくことをお勧めします。
まとめ
通勤手当は、自宅から勤務先までの通勤に要する交通費(鉄道・バス・マイカーなど)を福利厚生の一部として給与手当で支給します。企業に通勤手当の支給義務がなく、就業規則等で支給条件を定める必要があります。
他の給与手当と異なり一定条件下で非課税ですが、社会保険の算定対象に含まれます。
鉄道・バス・マイカーなど交通手段ごとに計算方法が異なりますので、煩雑です。
そして「経済的かつ合理的」な経路判定のためのチェック業務に負担を感じている担当者は少なくありません。
通勤費管理システムの「らくらく通勤費」なら、通勤手当の申請承認、経路チェックなどの業務を大幅に削減します。また、支給計算や払戻し計算、課税・社会保険計算を自動化することが出来ます。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。