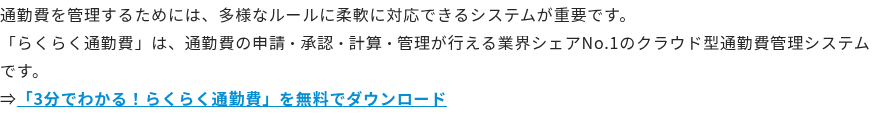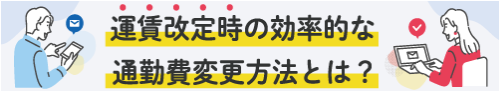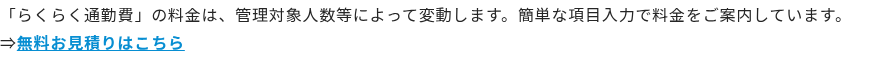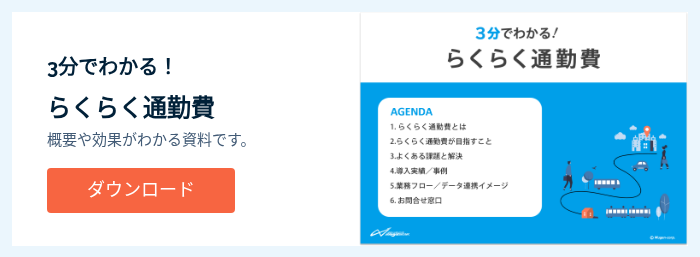通勤経路の申請方法をわかりやすく解説
監修者:佐川豊
この記事の目次
入社や、転居・転勤の際に行う通勤手当の申請。システム化されていればどのような通勤方法でも簡単に申請することが出来ますが、手作業の場合はいろいろと調べて通勤申請を行わなければなりません。
この記事では通勤経路の申請について解説します。
通勤経路とは
通勤経路とは、自宅から勤務先までの通勤に使う道のりのことです。電車やバスなどの公共交通機関、自動車・バイクや自転車などの交通用具、徒歩などの交通手段によって道のりは異なります。
一般的に、「最も経済的かつ合理的な経路および手段」による通勤にかかる費用に対して、通勤手当が支給されます。
なお、通勤手当の支給条件は企業ごとに異なり、就業規則などで定められています。場合によっては、子どもの保育園の送迎や家族の介護のための立ち寄りも、通勤経路として認められることがあります。
通勤経路の申請をする際は、一般的に以下の情報を記載します。
・出発地、目的地(自宅、勤務地など)
・利用する交通手段(電車、バス、自動車、自転車など)
・利用する駅やバス停
・通勤距離と所要時間
・公共交通機関を利用する場合は運賃
この申請内容は、通勤中に事故やケガがあった場合の「通勤災害」の労災認定にも使われるため、正確な情報を記載することが重要です。
地図を活用した通勤経路申請の方法
通勤費管理システムを使わない通勤経路申請の場合、以下のような方法があります。
・紙での申請
・ExcelやWordでの申請
・人事・労務システムを使った申請
どの方法でも、自宅から勤務先までの通勤経路を示す地図の添付が必要になることが多いです。
紙やExcel・Wordで申請する場合は、GoogleマップやYahoo!地図などのオンライン地図サービスを使うと、通勤経路の地図を簡単に作成できます。
これらの地図サービスを使えば、方角や位置関係が視覚的にわかりやすく表示されるため、手書き地図が苦手でも描きやすくなります。
Googleマップなどオンライン地図の使い方(通勤経路用)
ここではGoogleマップを例にご紹介します。Googleマップでは出発地と目的地を入力することで、経路を表示させることが出来ます。
1.「出発地」に自宅住所を入力
2.「目的地」に勤務先の住所を入力
3.表示された経路を確認し、距離・所要時間・乗換・運賃などをメモします
4.地図を印刷またはPDF保存して、申請書に添付します
・メールで申請する場合は、PDFファイルを添付します
管理者側の注意点として、管理担当者が通勤経路を確認・管理する際には、毎回住所を入力して経路を表示させる必要があります。また、地図情報の保管方法にも工夫が必要です。
参考:Googleマップ
通勤経路申請に記載する項目
通勤経路の申請を地図等の絵や画像を添付せず文章のみで申請する場合には、簡潔でわかりやすく記載することが大切です。通勤手段ごとに書き方のポイントが異なります。
【電車通勤の場合】
以下の項目を記載します。
・自宅から最寄り駅までの移動手段(徒歩、自転車など)と所要時間
・利用する駅名(乗車駅・乗換駅)
・利用する路線名
・各路線の所要時間
・各路線の運賃
・降車駅から勤務先までの徒歩時間
【バス通勤の場合】
以下の項目を記載します。
・自宅から最寄りのバス停までの移動手段(徒歩、自転車など)と所要時間
・利用するバス停名(乗降バス停名)
・バス会社名
・各路線の所要時間
・各路線の運賃
・降車バス停から勤務先までの徒歩時間
【自動車・自転車・徒歩通勤の場合】
以下の項目を記載します。
・通勤経路(主な道路名や交差点名など)
・通勤距離
・所要時間
・方角や目印となる場所(例:〇〇交差点、△△通りなど)
※できるだけわかりやすいルートを選び、目印を含めて記載すると、確認がスムーズになります。
電車通勤の記載例
電車のみの場合、駅までの徒歩時間や乗換時間、運賃なども含めて記載します。運賃は就業規則などの規定に従って「きっぷ」又は「ICカード」の金額を記載します。定期代支給の場合は、定期代も記載します。
【記載例】
自宅
↓(徒歩10分)
◯◯駅
↓(◯◯線 20分/運賃261円、1ヶ月〇〇円、3ヶ月○○円、6ヶ月〇〇円)
◯◯駅
↓(徒歩2分)
◯◯駅
↓(◯◯線5分/運賃167円、1ヶ月〇〇円、3ヶ月○○円、6ヶ月〇〇円)
◯◯駅
↓(徒歩10分)
勤務先
バス通勤の記載例
バス通勤の場合は、企業の就業規則等に定められた条件を満たしているか確認が必要です。例えば、「自宅から最寄駅までの距離が1.5km以上の場合にはバス代を支給」「自宅から勤務地までの距離が2km以上の場合にバス代を支給」などの条件です。定期代支給の場合は、定期代も記載します。
距離の証明には、地図サービスでの距離計測や、バス会社が発行する距離証明書の提出を定めている企業もあります。
【記載例】
自宅
↓(徒歩5分)
◯◯バス停
↓(◯◯バス 20分/5km/運賃220円、1ヶ月〇〇円、3ヶ月○○円)
◯◯バス停
↓(徒歩5分)
勤務先
自動車・自転車・徒歩通勤の記載方法
通勤手当は距離に応じて支給されるため、正確な距離計測と申告が重要です。
【記載例】
自宅
↓
東方向に直進
↓
◯◯交差点を左折
↓
◯◯道路を右折し、国道○号線を南下
↓
○○通りを直進
↓
○○交差点を左折
↓
勤務先
通勤距離:15キロ 所要時間:30分
自動車通勤の場合、通勤経路の記載に加え多くの場合以下の書類の提出が必要とされます。
・運転免許証のコピー
・車検証のコピー
・保険証券のコピー
・誓約書
自転車通勤の場合、東京都では駐輪場の確保が義務化されています。また、多くの自治体では自転車保険の加入が義務化されています。
通勤経路の記載に加え多くの場合以下の書類の提出が必要とされます。
・自転車保険証券のコピー
・駐輪場証明
・誓約書
徒歩通勤の場合は、通勤手当が支給されないケースもありますが、通勤経路の申請は必要な場合が多いです
複数交通機関を利用時の記載方法
バスと電車など複数の交通機関を乗り継ぐ場合は、乗換地点や路線名を明確に記載します。
【記載例】
自宅
↓(徒歩5分)
○○バス停
↓(○○バス 15分/5km/運賃220円)
○○駅入口バス停
↓(徒歩3分)
○○駅
↓(○○線 約30分/運賃377円)
○○駅
↓(徒歩5分)
勤務先
手書き略図の作り方
企業によっては通勤経路申請に手書きの略図の提出が必要な場合もあります。
手書きで通勤経路の略図を作ることが苦手な人が多いと思いますが、以下のポイントを押さえると誰でもわかりやすい地図が作れます。
①方角と縮尺を決める
・地図の上を「北」にするのが基本です。一般的な地図と同じ向きにすると、見る人にとって理解しやすくなります。
・Googleマップなどの地図サービスを参考にして、自宅から会社までの全体が見える縮尺で描きます。
②目印を効果的に配置する
・通勤経路上にある目印になる建物や施設(学校、病院、銀行、コンビニなど)を記載すると、位置関係がわかりやすくなります。
・道路名、交差点名、信号機なども記載すると、さらに明確になります。
・長い直線道路の場合は、中間地点の目印や距離の記載も有効です。
・自宅や会社は色を変えたり、少し大きく描くことで、地図の中で目立たせます。
③経路を明確に示す
・通勤ルートは、赤ペンで線を引いたり、矢印を使って道順を示すと、見た人がすぐに理解できます。
④必要最低限の情報に絞る
・細かすぎる情報はかえって分かりづらくなるため、実際に通るルートを想定して、シンプルに描きます。
・細い道は省略し、大きな道路を中心に描くと見やすくなります。
・緩やかなカーブなどは、直線で表現しても問題ありません。
正しい通勤経路申請のコツ
通勤経路を正しく申請するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
・就業規則等の通勤規定を事前に確認する
申請前に、就業規則や通勤に関する社内ルールを確認します。特に以下の点を把握しておく必要があります
・利用できる交通手段の条件
バス代支給が認められる距離
自転車通勤が認められるかどうか
・定期代支給期間
1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月などどの期間で申請できるか
・実費精算の条件
定期券以外の通勤費が認められるケース
・最安、最短の通勤経路を確認
「経済的かつ合理的な経路」かどうかを確認します。最短や最安の経路のみを認める企業もあります
・通勤経路を証明する資料の準備
申請内容の正当性を示すために、通勤経路を証明する資料を添付することが望ましい
通勤経路を証明する資料は、乗換案内のスクリーンショットや定期券の写しなどが一般的です
・通勤経路に変更があった場合の速やかな申請
以下のような変更があった場合は、速やかに申請内容を更新します
・転居(住所変更)
・異動による勤務地の変更
・勤務形態の変更(勤務時間・勤務日数等)
・特別な事情がある場合の申請
以下のようなケースでは、通勤手当の申請が必要になることがあります
・通勤途中で子どもの保育園送迎や介護の送迎をする場合
・複数の勤務地に通勤する場合
関連記事:通勤費の管理で、共通のお悩みや課題とは?
経済的かつ合理的な経路とは
多くの企業では、通勤手当の支給にあたり「最も経済的かつ合理的な経路」を基準としています。この基準は、以下のように定義されることが一般的です。
経済的:運賃が安価であること
合理的:所要時間や移動距離が短いこと
しかし、経路を検索してみると、安いが時間がかかる経路や、高いが時間が短い経路など、複数の選択肢が存在します。どの経路を「経済的かつ合理的」と判断するかは、企業ごとの方針によって異なります。
そのため、通勤費の申請や審査を円滑に進めるためには、企業として「経済的かつ合理的な経路」の判断基準を数値で明確に定めておくことが有効です。これにより、担当者や責任者の判断負担を軽減することができます。
【判断基準の例】
・最も安価な経路と比較して、運賃が30%以内の差であれば「経済的」とみなす
・最も安価な経路よりも所要時間が20分以上短縮される場合は、多少運賃が高くても「合理的」として認める
関連記事:経済的かつ合理的な通勤費支給方法
特別な事情による通勤経路について
子どもの保育園送迎など、特別な事情により通常とは異なる通勤経路(遠回りとなる経路)を申請する場合でも、規定に基づいて認められるケースがあります。
このような申請を行う際には、以下の点に留意が必要です。
・遠回りとなる理由を明確に記載すること
例:保育園の送迎、介護施設への立ち寄りなど
・申請経路を示す地図等の資料を添付すること
通勤ルートの具体的な経路を視覚的に示すことで、申請内容の妥当性を説明しやすくなります
判断基準や申請方法は企業ごとに異なるため、事前に就業規則や通勤手当の運用ルールを確認することが重要です。
通勤費の申請は「らくらく通勤費」で効率的に
ここまで通勤経路の申請方法を解説しましたが、様々なツールを利用しなければならなかったり手書きをしたりと面倒さを感じられたのではないでしょうか。
通勤費の申請は、乗換経路や地図の確認・記入など、申請する頻度は高くなくても手間に感じる作業が多くあります。また、管理担当者も申請内容を一つひとつ確認する必要があり、複数のツールを使って対応するため煩雑な業務に時間を取られているでしょう。
通勤費管理システム「らくらく通勤費」なら、申請から承認、金額計算、管理までを一元化でき、業務の効率化が図れます。通勤規定に合わせた柔軟な設定が可能で、従業員と管理者双方の負担を軽減し、申請の正確性とスピード向上にも貢献します。
まとめ
通勤費の申請は、正確な経路の把握と、自社の通勤規定に記載されている支給条件の理解が重要です。
管理者側は「経済的かつ合理的な経路」の判断を正しく行い、不公平のない通勤費支給を行わなければなりません。
通勤費の申請や判断・計算の負担を軽減するには、通勤費管理システムの導入が有効です。業務効率化や、適正化のために是非システム化もご検討ください。
監修者佐川 豊

株式会社無限 PI事業部 営業部 エバンジェリスト
業務系パッケージベンダーなどを経て無限入社。らくらく通勤費のセミナーやマーケティング・プロモーションを担当。